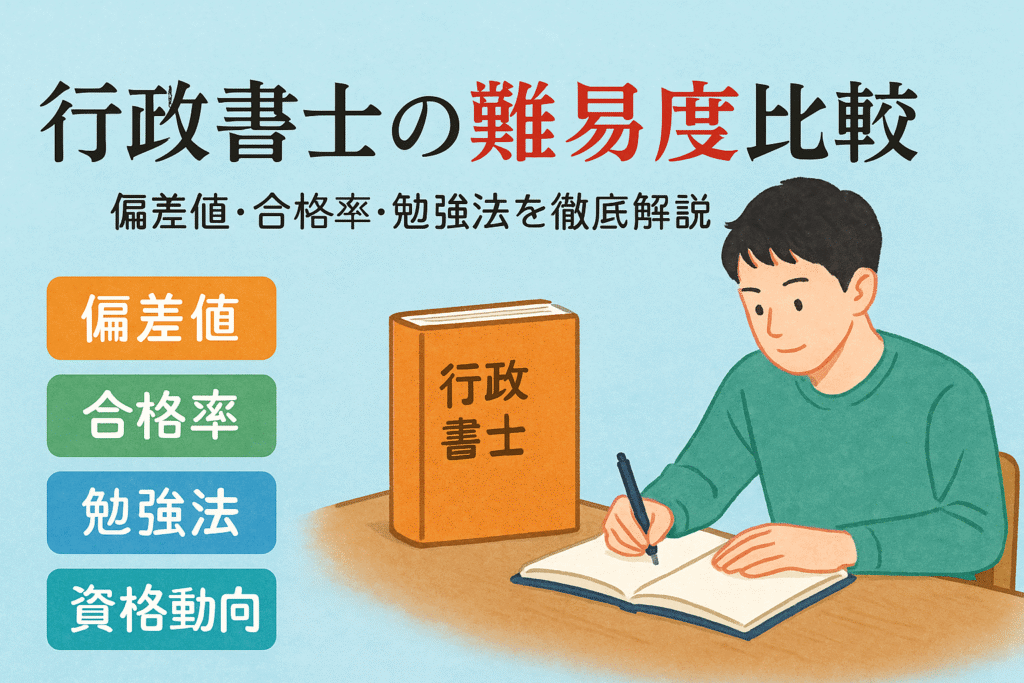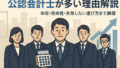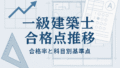「行政書士の資格は、本当に難しいの?」──そう疑問に思っていませんか。
実は行政書士試験の合格率は【2024年度】で11.7%。法律分野の国家資格の中では7番目の難易度とされ、年々出題傾向や受験者層も変化しています。他士業と比較しても、行政書士は司法書士(合格率3.6%)、社労士(6.4%)などより挑戦しやすい一方で、独学合格を目指す場合は「600時間以上」の学習時間が目安とされており、一歩踏み出すには明確な戦略が必要です。
「自分でも合格できるのか」「独学と講座、どちらが向いている?」と迷っている方も多いはず。
このページでは最新実績や具体的なデータをもとに、行政書士試験の難易度や合格率、ランキングの全体像を詳細に解説します。最後まで読むことで、あなたに最適な合格への道筋も見つけられるでしょう。
「自分には無理かも…」とあきらめる前に、実際の合格者のリアルや資格取得後のキャリアもぜひチェックしてください。
行政書士の難易度ランキングの全体像と国家資格内での位置づけ
行政書士は、法律系国家資格の中で高い人気を誇る資格です。その難易度は毎年多くの受験生から注目されています。一般的に行政書士は、司法書士や弁護士などと比較した難易度はやや低いものの、近年は出題傾向の変化や試験範囲の広さから決して簡単な資格とは言えません。民間資格や他の国家資格と比べて実務や社会的影響力が大きく、行政手続きや契約書作成など幅広い分野で活用できるため、資格難易度ランキングでも常に上位に位置しています。
行政書士の受験資格に年齢や学歴制限はなく、誰でもチャレンジできる点も特長ですが、その一方で合格率は10%前後と現実的には高い学習量と準備が求められます。下記のようなランキング表で、行政書士の国家資格内での立ち位置を確認しましょう。
| 資格名 | 合格率 | 平均勉強時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 約30% | 6000時間以上 | 非常に高い |
| 司法書士 | 3.5~4% | 3000時間 | 非常に高い |
| 社会保険労務士 | 6~7% | 1000時間 | 高い |
| 行政書士 | 10~12% | 600~1000時間 | やや高い |
| 宅地建物取引士 | 15~17% | 300~400時間 | 標準 |
このように、行政書士は8士業の中でも上位クラスの難易度で、社会的評価も高いポジションにあります。
行政書士とは|業務内容と資格の社会的役割
行政書士は、主に官公署への各種許認可申請や契約書・遺言書など法的文書の作成、企業の法務サポートといった幅広い業務を担う国家資格です。個人や企業の法的な課題を実務で支える存在として、弁護士・司法書士とともに「三大法律国家資格」に数えられることもあります。
社会的信頼性が高く、近年は女性や主婦層の取得事例や、専門知識を生かして独立・開業を目指す方が増加しています。行政手続きのオンライン化が進む現代においてもその役割は変わらず、今後も需要が高い職種と言えます。
国家資格難易度ランキングにおける行政書士の順位
行政書士は、国家資格難易度ランキングにおいて司法書士や弁護士、社会保険労務士についで高めの難易度に位置します。特に8士業の中では中上位にランクインしており、偏差値で表すと65前後という評価もあります。最近の合格率や、試験内容が問われる法律知識の深さ、膨大な勉強時間がその根拠です。
下記のポイントで他士業との比較ができます。
- 司法書士、弁護士はさらに高難度で合格率が低い
- 宅建士などは比較的短期間で合格可能
- 行政書士は独学でも合格できるが、しっかりした対策が不可欠
ランキング上では「取りにくい国家資格」として認識されますが、正しい学習法と計画があれば十分に狙える資格です。
難易度ランキングの評価軸とランキングの信頼性について
国家資格の難易度ランキングは、以下の基準で評価されるケースが一般的です。
- 合格率
- 必要な平均勉強時間
- 問われる専門知識や試験範囲の広さ
- 実務での活用度や社会的価値
これらの指標を総合的に判断して難易度が決定されています。行政書士試験は、合格率や勉強時間に加えて、試験問題の質や出題範囲の広さがランキングの根拠となっています。
ネット上のランキングや口コミにはばらつきがありますが、公的なデータや複数の専門家評価をもとに作成されたランキングは信頼性が高いです。行政書士試験は「難易度ランキングおかしい」という声もある中、実際は幅広い知識と応用力が必要な、本格的な国家資格と位置づけられています。
合格率の推移や偏差値比較から見る行政書士試験の実態
近年の合格率推移と変動要因
行政書士試験の合格率は、年によって変動がありますが、およそ10%前後で推移しています。下記の表に直近数年の合格率をまとめました。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 47,870 | 5,802 | 12.1 |
| 2022年 | 47,870 | 5,802 | 12.1 |
| 2021年 | 47,870 | 5,798 | 12.1 |
| 2020年 | 41,681 | 4,470 | 10.7 |
ここ数年は若干の上昇傾向にありますが、出題傾向の変化や受験者の層の広がりが影響しています。法律科目の出題内容の難化や、記述式問題の難易度調整によって合格者数が調整されています。
また、他の国家資格と比較しても合格率は決して高くはないため、行政書士試験の難易度は依然として高い水準を保っています。
年齢・性別・学歴別に見る合格率比較
行政書士試験は受験資格が広いため、学生から社会人、主婦、シニア世代まで幅広い層が挑戦しています。合格者の年齢構成や性別、学歴別の比率は以下の通りです。
| 属性 | 合格者割合(%) |
|---|---|
| 20代 | 22 |
| 30代 | 27 |
| 40代 | 25 |
| 50代 | 17 |
| 60代以上 | 9 |
| 性別 | 合格者割合(%) |
|---|---|
| 男性 | 61 |
| 女性 | 39 |
| 学歴 | 合格者割合(%) |
|---|---|
| 大学卒 | 56 |
| 高卒 | 24 |
| 専門卒・短大 | 14 |
| その他 | 6 |
幅広い年代・学歴の方が合格していますが、大学卒業者が多い傾向です。特に法律知識が活かせる法学部出身者の割合がやや高めです。女性合格者も年々増えており、多様なバックグラウンドの方が行政書士にチャレンジしています。
大学別や偏差値別の合格率傾向
行政書士試験は学歴要件がなく、誰でも受験可能ですが、出身大学や偏差値帯で見ると傾向があります。国公立大学や難関私大、法学部卒の受験者が合格率を押し上げている場合が多いです。
| 偏差値帯 | 合格者割合(%) | 主な出身大学例 |
|---|---|---|
| 65以上 | 21 | 早稲田大・慶應義塾大 |
| 60~64 | 17 | MARCH(明治・青学・立教ほか) |
| 55~59 | 28 | 日東駒専・地方国公立 |
| 54以下 | 34 | 社会人・高卒など多様 |
法学部以外の学部や社会人からの挑戦も多く、独学合格例も多数見られます。偏差値や出身大学による有利・不利は限定的ですが、学習計画と継続的な勉強が合格の鍵となっています。どの層でも十分に努力次第で行政書士試験への合格が可能です。
行政書士試験の出題科目と合格基準の詳細分析
行政書士試験は、法律系国家資格の中でも受験者数が多く、幅広い分野から出題されます。主な試験科目は行政法・民法・憲法などが中心で、それぞれの科目ごとの配点や特徴を正確に理解することが、効率よい学習への第一歩です。また、合格基準は明確に定められており、バランス良く得点することが不可欠です。出題形式や実施時期、受験資格に関する制度情報もあわせて知っておくことで、確実に試験対策を進められます。
主要科目(行政法・民法・憲法など)の配点と特徴
行政書士試験では、各科目の配点が合格戦略に直結します。主な配点と特徴は下表の通りです。
| 科目 | 問題数 | 配点(合計) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 行政法 | 19 | 76点 | 最重要。現実の行政業務に即した内容で頻出。 |
| 民法 | 9 | 36点 | 難易度高め。判例や条文理解が必須。 |
| 憲法 | 5 | 20点 | 基本文理解が問われ、独特の思考力が必要。 |
| 商法・会社法 | 5 | 20点 | 基本事項から応用まで幅広く出題。 |
| 一般知識 | 14 | 56点 | 情報通信・文章理解・時事など幅広い範囲。 |
行政法だけで総得点の約40%を占めているため、ここを重点対策すれば合格に近づきます。民法や憲法も基礎固めが重要ですが、一般知識では足切り制度があるため油断できません。
記述式問題の難しさおよび対策ポイント
行政書士試験では、三問の記述式問題(各20点、計60点)が出題されます。特に行政法・民法から出題されることが多く、法律知識だけでなく論理的な文章力も求められます。毎年、出題傾向や採点が厳しくなる傾向が見られるため、確実な得点源とするには十分な演習が必要です。
対策としては
- 過去問を繰り返し解く
- 模範解答の型を覚えて再現する
- 要件・効果を整理し、端的にまとめる練習を重ねる
ことがポイントです。記述で合格基準に達しない受験生も多いため、実務的な問題文の読み取り力も鍛えておきましょう。
試験実施日時や受験資格などの制度情報
行政書士試験は毎年11月の第2日曜日に全国一斉に実施されます。受験資格は年齢・学歴・国籍など一切問われず、誰でもチャレンジできる国家資格です。この点は資格難易度ランキング上でも高い人気の要因となっています。
主な試験概要は下記の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験日 | 毎年11月第2日曜日 |
| 受験資格 | 不問(誰でも受験可能) |
| 試験時間 | 3時間 |
| 試験地 | 全国各地の指定会場 |
| 申込期間 | 毎年7月頃に開始 |
この受験しやすさから、社会人・主婦・学生など幅広い層が受けており、法学部出身だけでなく独学高卒や他分野の出身者も多数合格しています。また、行政書士試験の難易度は国家資格でも高水準とされており、多様なバックグラウンドの受験生が挑戦している現状があります。
合格戦略|独学・通学・通信講座での選び方と勉強法ランキング
行政書士試験の合格を目指す際、独学・通学・通信講座のどれを選ぶかは、合格への効率や成功率に大きく影響します。それぞれの学習方法は、生活スタイルや学習経験、必要なサポートレベルによって最適な選択肢が変わります。ここでは、行政書士の難易度ランキングや他の国家資格と比較しながら、合格に近づく最適な学習戦略を詳しく解説します。
独学の実情と成功者による勉強法
独学で行政書士試験に合格した方の多くが口にするのは「テキストや過去問の徹底活用」です。独学は費用を大幅に抑えられる反面、自分で情報収集や勉強計画を立てる必要があります。実際、独学合格者には高卒や主婦、働きながらの方も多数おり、「独学は無理ゲー」と感じる方でも、継続的な学習と自己管理で合格が可能です。
おすすめの独学勉強法
- わかりやすい基本テキスト1冊を軸に反復学習
- 過去問を複数年分何度も繰り返す
- 理解に行き詰まったらネットや市販のQ&A本で補完
- 学習記録アプリや手帳で学習習慣を強化
独学は自学自習のコツを掴めれば、十分合格が可能なルートです。
予備校や資格スクールの特徴とメリット・デメリット
予備校や通信講座の利用は、行政書士試験での短期間合格を狙う方に有効です。予備校では体系的なカリキュラムや、生講義・ライブ配信での講義、わかりやすいオリジナル教材、個別指導サポートなどが充実しており、忙しい社会人や初心者も安心して受講できます。
主な特徴を比較表でまとめました。
| 学習方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 予備校 | 個別指導・的確なカリキュラム・質問対応が早い | コストが高い・通学の手間が必要 |
| 通信講座 | 自宅学習可・最新動画・テキストスマホ対応 | 自己管理力が必要・孤独感を覚える |
| 独学 | 費用が安い・自分のペースで進めやすい | 計画力・情報収集力が求められる |
スクール選びの際は「合格実績」「講義内容」「サポート体制」「教材の充実度」も重視しましょう。
効率的な勉強計画の立て方と過去問活用法
合格の鍵は、緻密な学習計画の立案とインプット・アウトプットのバランスです。行政書士試験は広範囲かつ理解・記憶の両方が問われます。効率的なスケジュール作成と過去問活用が必須です。
効率的な勉強計画のコツ
- 試験日までの全体スケジュールを逆算して立てる
- 「民法」「行政法」など主要科目に集中する期間を設ける
- 週ごとの進捗チェックと修正の習慣化
- 毎週or毎月ごとに過去問を繰り返すことで理解を定着
- 模試や答練で実戦慣れして合格基準点を体感する
過去問は年度別・分野別で最低5年分を数回解き直し、「なぜその答えになるか」を毎回解説で確認しましょう。知識の穴や苦手分野も可視化でき、得点力の向上につながります。
戦略的な学習法の選択と計画的な過去問演習こそが、行政書士試験の難易度を乗り越え、合格へ最短で近づく道です。
行政書士と他士業資格の難易度や収入の比較ランキング
行政書士は国家資格の中でも比較的取得しやすい部類に入りますが、合格するためには一定の学習時間と法律知識が求められます。多くの受験生が難易度や合格率、収入面で他資格と比較しながら進路を選ぶ傾向にあります。行政書士の位置づけを明確に把握するため、主要8士業とよく比較される国家資格の難易度や年収のランキングをまとめました。
| 資格名 | 合格率 | 目安勉強時間 | 難易度ランク | 推定年収 |
|---|---|---|---|---|
| 司法試験 | 30%未満 | 4000時間~ | 1位 | 約1000万円 |
| 司法書士 | 5%前後 | 3000時間 | 2位 | 約800万円 |
| 社会保険労務士 | 7%前後 | 1000時間 | 3位 | 約600万円 |
| 行政書士 | 10~15% | 600~1000時間 | 4位 | 約400~600万円 |
| 土地家屋調査士 | 9~10% | 750時間 | 5位 | 約500万円 |
| 税理士 | 15% | 2500時間 | 6位 | 約800万円 |
| 宅地建物取引士 | 15~18% | 350時間 | 7位 | 約450万円 |
| 公認会計士 | 10%未満 | 3000時間 | 8位 | 約800万円 |
行政書士試験は合格率10~15%とされていますが、独学での合格も十分可能です。学歴や大学の偏差値に関係なく広く門戸が開かれており、受験資格に制限がないことも特長です。上記ランキングは難易度・取得後の年収・学習負担のバランスを考慮しています。
行政書士の年収実態と性別・雇用形態別分析
行政書士の年収は、働き方や性別によって大きく異なります。
個人で事務所を開業する場合と、企業や士業法人へ就職する場合では収入に差が生じやすいです。
| 勤務形態 | 平均年収 | 備考 |
|---|---|---|
| 独立開業 | 300~800万円 | 実務経験や営業力の影響が大きい |
| 企業雇用 | 300~450万円 | 安定するが大幅な増収は難しい |
| 女性行政書士 | 250~400万円 | 育児や時短の選択肢もあり |
| 男性行政書士 | 350~600万円 | 独立型が多い |
行政書士の年収に関して、「年収が低い」「やめとけ」といった声も見受けられますが、これは開業した場合の営業力や得意分野、在籍地域による影響が大きいためです。女性も増加傾向で、柔軟な働き方を選べる職業でもあります。
司法書士・社労士との難易度や給与差の比較
司法書士や社会保険労務士(社労士)と比較すると、行政書士は合格までの学習負担がやや軽いとされています。ただし収入や社会的評価には明確な違いがあり、キャリア設計の参考になります。
| 資格名 | 合格率 | 必要勉強時間 | 平均年収 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 司法書士 | 約5% | 2500~3000h | 700~900万円 | 非常に高い |
| 社労士 | 約7% | 1000時間 | 500~600万円 | 高い |
| 行政書士 | 10~15% | 600~1000h | 400~600万円 | やや易しい |
司法書士は試験科目数が多く、合格まで複数年かかることも珍しくありません。社労士も年々難化傾向にあり、行政書士は「比較的簡単に取れる国家資格」として人気です。それでも充分な学習量は必要であり、独学でも挑戦しやすい点がメリットです。
人気・生き残る士業ランキングおよび資格の将来性
士業の人気や将来性は年々変化しています。特に行政書士を含む八士業は、依頼内容や法律改正、市場動向でニーズに差が生じやすい現状があります。
- 弁護士や公認会計士、司法書士の難易度・年収は依然高いですが、新規参入は難しくなっています。
- 行政書士は法務やビジネス支援分野で新しい需要が増加傾向です。
- 社会保険労務士や宅建士も需要安定のため、資格取得者は増加中です。
- 「資格カースト」「食える士業」「生き残る士業」と呼ばれる分野では、行政書士は中堅~上位に位置します。
最近では副業や女性の独立希望、専門職へのキャリア転換としても行政書士が選ばれています。今後も社会ニーズの変化やデジタル化に対応できる士業が、引き続き安定した需要を持つ傾向です。
実際の合格者や受験者から見た行政書士難易度のリアル評価
合格者の成功体験談と独学でのリアル
行政書士試験に合格した受験者の多くは、独学で合格を果たしています。特に仕事や育児と両立しながら、限られた時間で効率的に学習を進めた人も少なくありません。
以下に、独学合格者に多い学習方法と勉強時間の目安をまとめます。
| 学習方法 | 特徴 | 平均勉強時間 |
|---|---|---|
| 独学 | テキストや過去問を活用、自分のペースで進行 | 600~1000時間 |
| 通信講座 | 専門カリキュラムと動画で効率アップ | 500~800時間 |
| 予備校・通学 | 講義とフォロー体制が充実 | 400~900時間 |
独学でのポイントは、法令知識や過去問演習を徹底することです。また、専用アプリや効率的なテキストの活用が合格までの近道になるケースも多くみられます。
挫折や苦労の声|難易度の壁および試験の課題感
行政書士試験の難易度は決して低くありません。合格率は10%前後で推移しており、「途中で挫折した」「勉強時間の確保が難しい」といった声もしばしば聞かれます。
苦労しがちなポイントとしては以下のようなものが挙げられます。
- 範囲が広く、民法や行政法の理解に時間がかかる
- 法律的思考になじめないと問題が解けない
- 論述問題や記述式問題への対応が難しい
- モチベーションの維持が課題
このため、合格者の多くは計画的な学習やスケジュール管理、定期的な模擬試験の活用などで壁を乗り越えています。また「一発合格は難しい」「複数年かけて合格した」という人も多数います。
年齢・職業別の合格状況や学習形態の多様性
行政書士試験の合格者は年齢や職業も多様です。近年では主婦や高卒、高齢者、社会人、学生まで幅広い層が合格を果たしています。
| 年齢層 | 特徴 | 学習スタイル |
|---|---|---|
| 20代 | 法学部出身が多い | 独学・予備校が多数 |
| 30~40代 | 社会人や主婦が増加 | 独学・通信講座が主流 |
| 50代以上 | 定年後の新たな挑戦として受験 | 独学・オンライン講座 |
職業で見ると、会社員や官公庁勤務はもちろん、パートや専業主婦、フリーランスまで様々です。合格を目指す理由も就職・転職、独立開業、自己研鑽など多岐にわたります。
このように、多様な背景を持つ人が合格できる一方、学び方や対策も人それぞれで、適切な教材選びと自分に合った学習計画が成功へのポイントとなります。
行政書士取得後に期待できるキャリアパスや活かし方
行政書士としての実務内容や業務範囲
行政書士の主な業務は、官公庁への各種許認可申請書類の作成や提出代理、契約書・遺言書・内容証明文書の作成、法人設立手続きなど多岐にわたります。特に中小企業支援や許認可申請のプロフェッショナルとして活躍でき、クライアントの課題解決を幅広くサポートします。
幅広い分野で携わることができるため、建設業、運送業、飲食業など業種ごとの専門性も重要です。行政手続きのほか法律知識も要求され、顧客との信頼関係や交渉力も問われます。下表は行政書士の主な業務範囲です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許認可申請 | 建設業、運送業、外国人ビザ、飲食業など |
| 標準業務 | 契約書・遺産分割協議書・遺言書作成、内容証明 |
| 法人設立 | 会社・NPO法人等の設立書類作成、定款作成など |
| コンサルティング | 企業経営・起業支援、補助金・融資申請のアドバイス |
独立開業のメリット・デメリットおよび開業手順
行政書士は受験資格に学歴や年齢制限がなく、合格後すぐに独立開業が可能な士業です。独立することで自由な働き方や高収入を狙えます。年収レンジは幅広く、実績や営業力次第で大きく変わりますが、自分の努力が直接反映される環境といえます。
独立開業のメリット
- 資格取得後すぐに開業できる
- 自分の裁量で業務選択や働き方を決定可能
- 成功すれば高い年収や社会的信頼を得られる
デメリット
- 収入が安定するまで時間がかかることが多い
- 顧客獲得のため営業活動が不可欠
- 法律知識に加え経営やマーケティング力も必要
| 開業手順 | ポイント |
|---|---|
| 日本行政書士会連合会へ登録 | 合格後、都道府県会へ入会 |
| 事務所の開設・登記 | 業務エリア・ターゲット選定 |
| 必要設備の用意 | 電話・パソコン・情報セキュリティ |
| 営業・マーケティング開始 | ネット集客・専門分野のPR |
企業内行政書士や関連職種でのキャリア形成
行政書士資格は独立開業だけでなく企業での活躍にも生かせます。例えば、総務部門や法務部門でのコンプライアンス管理、契約書作成、各種申請プロセスの効率化に強みを発揮します。また、建設・不動産・国際取引をはじめとした業界で資格保有者が重宝されています。
行政書士資格をきっかけに、他士業へのステップアップや、社会保険労務士・司法書士・宅地建物取引士といった国家資格とダブルライセンスを狙う方も多くいます。また、女性や主婦でも独学で資格を取得し、時短勤務や在宅ワークとして柔軟に働ける点も注目されています。
- 総務・法務分野での専門性強化
- 士業事務所や企業法務部でのキャリアアップ
- 他資格と組み合わせ生涯価値の向上
- 柔軟な働き方によるワークライフバランスの実現
行政書士資格は、「知識」「スキル」「実務経験」を積むことで、多様なキャリアパスを描くことができる国家資格です。
行政書士試験に関するよくある質問(Q&A)集
難易度や合格ラインに関する質問
行政書士試験の難易度は国家資格ランキングでも中上位に位置します。直近の合格率は約10〜12%前後で、法律系国家資格のなかでは比較的手が届きやすい水準ですが、決して「誰でも受かる」試験ではありません。科目は法令科目(行政法・民法など)が主軸で知識の深さと幅が問われます。
偏差値換算では「65」前後、大学に例えると有名国公立〜MARCHクラスが目安と言われています。合格基準点は300点満点中180点以上(かつ科目ごとの足切りあり)と設定されています。志望者は自身の学力や基礎知識を客観的に見極め、しっかり対策を進めることが重要です。
勉強期間や教材選びに関する質問
合格までの必要勉強時間は一般的に600〜1,000時間が目安とされます。社会人の場合、1日2時間×10ヶ月程度のペースが現実的です。効率的な学習には、行政書士専用のテキストや過去問題集、通信講座が利用されています。
特に独学者は、わかりやすい解説と十分な演習量がある書籍やアプリを選ぶことが合格の鍵です。以下のポイントで教材をチェックしましょう。
- 法令科目に強い解説が付いている
- 過去問・予想問題が充実
- 初学者にも対応したカリキュラム構成
- 解答解説が詳細
公式問題集や人気テキスト、動画講座も併用すると理解が深まります。
資格取得後の活用や年収に関する質問
行政書士は法律手続きの専門家として幅広い分野で活躍しています。年収は働き方によって異なり、自身で事務所を開業した場合は300〜600万円が平均とされ、成功すると1,000万円以上も目指せます。一方、企業勤務の場合は雇われ行政書士として年収300万円前後というケースもあります。
女性や主婦の独立開業も増えており、多様な働き方が可能です。行政書士の仕事内容としては、許認可申請、契約書作成、法人設立相談など多岐にわたります。将来性や「食える士業」として注目されていますが、収入面の現実もきちんと把握しておく必要があります。
独学とスクール利用の賢い使い分けについて
独学での合格者も多数いますが、短期間で効率よく合格したい場合や法学部出身ではない方は通信講座やスクールの活用もおすすめです。スクールのメリットは、体系的なカリキュラム、分かりやすい講義、疑問点をすぐ聞けるサポート体制が整っている点です。
独学派にも、YouTube動画解説やスマホアプリを併用する人が増えています。自分の学習スタイルや生活リズムに合わせて、教材・講座を「必要な部分だけピンポイントで使う」やり方も効果的です。
複数資格併願時に気をつけたい注意点や比較
行政書士以外にも司法書士、社会保険労務士(社労士)、宅地建物取引士(宅建)など、士業資格の難易度ランキングはさまざまです。
| 資格名 | 合格率 | 難易度(偏差値目安) | 学習時間目安 | 年収目安(独立) |
|---|---|---|---|---|
| 司法書士 | 3%前後 | 偏差値70以上 | 2,000時間以上 | 700万円~ |
| 行政書士 | 10~12% | 偏差値65前後 | 600~1,000時間 | 300~600万円 |
| 社会保険労務士 | 6~7% | 偏差値60前後 | 800~1,200時間 | 300~500万円 |
| 宅建 | 15~17% | 偏差値55前後 | 300~500時間 | 300~500万円 |
複数併願する場合は出題範囲や時期重複に注意し、基礎から応用へ無理なくステップアップできる計画を立てましょう。どの資格にも独特の難しさがあるため、自分の将来像を明確にしながら取得順序や優先度を選ぶことが大切です。