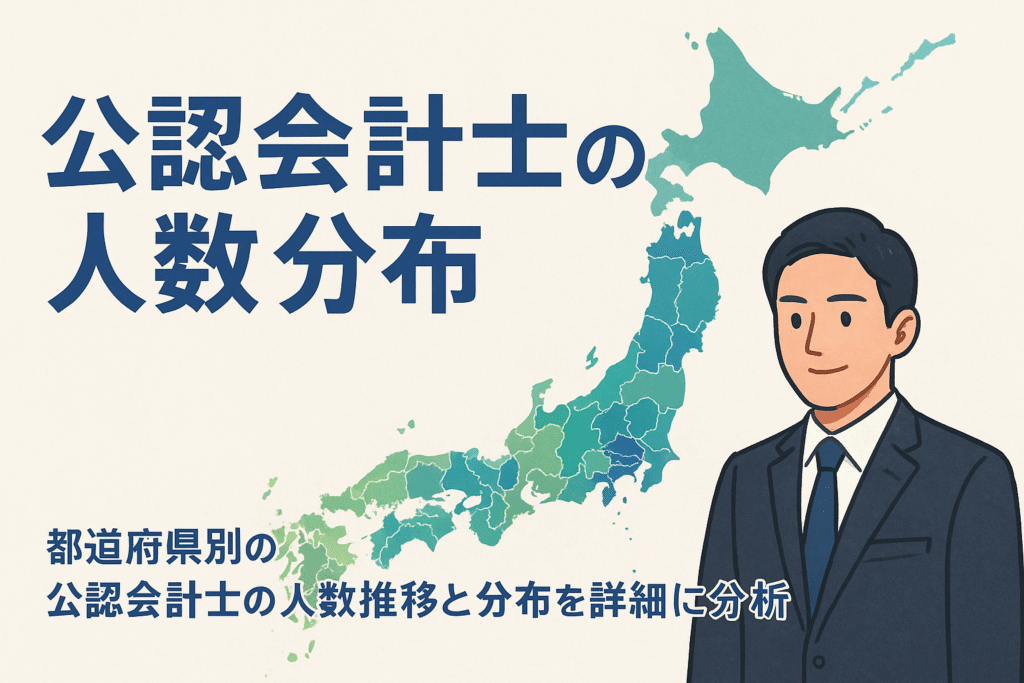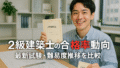近年、公認会計士の人数が大きく変化していることをご存じでしょうか。本会員として登録されている公認会計士は【2024年末時点で約40,000名】を突破し、うち新規合格者も年間1,500人を超えるなど、その存在感はますます高まっています。その一方で、都市部に会計士が集中し、【東京都・大阪府・愛知県の3都府県だけで総人数の6割以上】を占めるなど、地域ごとの偏在も深刻な課題となっています。
また、公認会計士の年齢層を見ても、近年は【30代以下の若手の割合が増加】し、女性会計士も全体の1割を超えるなど、多様化が進んでいます。他の士業と比べてみても、公認会計士は税理士や弁護士よりも少人数かつ専門性が極めて高いため、独自の求人市場を形成しています。
「どこに、どれだけの公認会計士がいるのか?」「なぜ都市部と地方でこれほど人数差があるのか?」――こうした疑問を持つ方のために、最新の人数データと推移、地域・世代・性別ごとの特徴を徹底解説しています。
本記事を読めば、公認会計士の実態を正確に把握し、転職やキャリアアップ、進路選択に役立つ具体的な数字と事実が手に入ります。今のうちに、今後の業界動向を押さえておきませんか?
公認会計士の人数とは何か?定義と集計方法を徹底解説
公認会計士の人数は、日本公認会計士協会が正会員(登録公認会計士)を基準に毎年公式発表しており、最新統計では全国で約4万人規模とされています。この数値は、監査・コンサルティング・財務など幅広い分野に従事する士業全体の規模を示しています。
会員数のカウント基準については、現役の正会員に加え、準会員(試験合格後、登録要件を満たしていない人)や休会中会員も分類されていますが、求人や社会的需要のデータとして用いられるのは原則として正会員のみです。日本公認会計士協会が定期的に公開する年次データが最も信頼でき、全国・都道府県別や年齢層別に精緻に把握されています。
公認会計士は、高度な会計監査や財務コンサルティング業務の他、IPO支援や企業再生、M&Aアドバイザリーなどでも活躍し、経済社会において欠かせない役割を持っています。
公認会計士と準会員(試験合格者)の人数区分は正式会員との違いと登録要件を詳細に解説
日本の公認会計士は「正会員」と「準会員」に区分されます。正会員は全ての実務要件と協会登録を満たした士業者で、会計監査や法定業務を担えます。一方、準会員は公認会計士試験に合格したものの実務補修や補助業務など一部要件未達の段階です。
区分のポイントは下記の通りです。
-
正会員:公認会計士試験合格、実務経験と修了考査合格、協会登録完了
-
準会員:試験合格のみ(実務経験中の段階も含む/監査法人勤務の場合も多い)
準会員も全国に1万人規模で存在し、各都道府県の監査法人や一般企業で経験を積んでいます。なお、試験合格後に正会員となるには3年以上の実務と公式研修が不可欠です。
本データ把握の際には「正会員」の人数が市場分布や社会的評価の中心指標として採用されています。
公認会計士人数の公式データ収集方法と公開統計の信頼性は協会発表、監査法人別集計、地方自治体情報を比較
公認会計士の人数統計は、主に日本公認会計士協会による年次公表データが基準となります。最も信頼性が高く、多くの情報媒体や教育機関、転職メディアでも参照されています。
データ収集・集計の主な流れは下表の通りです。
| データソース | 主な特徴 |
|---|---|
| 日本公認会計士協会 | 正会員・準会員を独自登録システムで精緻に集計 |
| 主要監査法人(あずさ・トーマツ等) | 法人単位の会計士在籍数やエリア分布に強み |
| 地方自治体/地方協会 | 都道府県ごとの細かな人数動向、地方での偏在状況を把握 |
協会公表のほか、監査法人ごとの会計士割合や、都市部・地方のバランスも公知データで分かるため、市場分析や将来展望の根拠として活用されています。近年は地方の会計士希少性や女性比率の推移など、多角的な統計も重要視されています。
公認会計士の人口比率と他士業(税理士・弁護士)との人数比較は国家資格としての相対的ポジション
公認会計士は、日本の国家資格の中でも比較的少数で希少性の高い職種です。ほかの主要士業数と比較すると分かりやすく、以下のようなバランスとなっています。
| 資格職種 | 推定人数 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 公認会計士 | 約40,000人 | 会計監査、コンサル、財務、IPO支援 |
| 税理士 | 約80,000人 | 税務申告、税務相談、企業会計支援 |
| 弁護士 | 約45,000人 | 法律相談、裁判業務、企業法務 |
公認会計士は人口比で約3,000人に1人の割合となり、他士業と比べても専門性の高さが際立ちます。特に大手監査法人には多数が集中している一方、地方では100人を下回る県もあり、その希少性が雇用市場や独立開業ニーズを押し上げています。
このように、公認会計士の人数や人口比は、他士業と比較した際にも社会的な重要度やキャリアパスの多様性を映し出しています。
公認会計士人数の最新推移と過去20年間の増減要因分析
年次別公認会計士総数の変遷は受験者数・合格者数・登録者数の経年推移をグラフとともに
公認会計士の人数は、毎年の試験受験者数、合格者数、そして最終登録者数の推移に大きく左右されます。直近20年を見ると、試験制度の見直しや年齢分布の多様化によって増減に変化が見られます。以下は主要な経年データです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 登録者数 | 総人数(累計) |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 約42,000 | 1,469 | 1,208 | 約16,500 |
| 2010年 | 約24,000 | 2,041 | 1,682 | 約26,200 |
| 2015年 | 約11,000 | 1,102 | 920 | 約31,200 |
| 2020年 | 約10,000 | 1,335 | 1,058 | 約36,700 |
| 2024年 | 約8,500 | 1,297 | 990 | 約38,000 |
ポイント
-
2006年の試験制度改正以降、合格者数は増加し、登録者の若年化も進みました。
-
近年は受験者数が減少傾向ですが、合格率は比較的高めで推移しています。
-
累計人数は着実に増えており、2024年時点で約38,000人に達しました。
影響を及ぼす法制度や社会的背景は金融審議会の報告や内部統制監査制度の導入などの影響を深掘り
公認会計士の人数推移には、周辺環境の変化が大きく影響しています。
主な影響要因
-
金融審議会報告
2003年以降、金融審議会の提言により会計基準や監査体制が再構築され、弁護士や税理士と同等の社会的信用性の強化が進みました。
-
内部統制監査制度(J-SOX)の導入(2008年)
上場企業に内部統制報告書の義務化が施行され、監査法人やあずさ監査法人など大手事務所を中心に公認会計士の需要が拡大しました。
-
高等教育機関との連携
出身大学の多様化が進み、難関大学のみならず中堅大学や私立大学ランキングにも変化が見られます。
このような流れの中で、実務家として企業で活躍する比率が高まり、求人・転職市場にも大きな影響を与えています。
近年の傾向と社会・企業ニーズの変動は合格者微増と修了考査受験者減少の背景分析
近年は「社会の変化」「企業ニーズ」に応じて公認会計士の人数動向も変化しています。
-
合格者数の微増
2020年以降、受験者数は減少傾向ですが、試験の難易度バランスにより合格者数は1,200人前後で安定しています。登録まで進む修了考査受験者の数は減少しつつあるものの、全体人数は増加中です。
-
企業内会計士の増加
従来は監査法人勤務が主流でしたが、コンサルティングやIPO支援、経営企画分野など企業内での活躍も目立ちます。社会からの信頼度とともに、監査以外の業務需要が拡大しました。
-
主な要因の一覧
- 女性会計士や若年層の増加
- AI・デジタル化への対応ニーズ
- 地方地域での人数希少性(沖縄などは依然として低水準)
今後も公認会計士に期待される役割や働き方は多様化が進み、業務内容や就職先もさらに広がると見られています。
都道府県別・地域別の公認会計士人数の実態と地域特性分析
都市部(東京・大阪・名古屋)に公認会計士人数が集中する理由と統計データ
日本全国に約38,000人とされる公認会計士の多くは、大都市圏に集中しています。特に東京・大阪・名古屋の三大都市は、監査法人や大手企業が集積し、監査やコンサルティング業務が豊富なことが圧倒的な吸引力となっています。最新の会員登録データでも、東京で約16,000人、大阪で約5,000人、名古屋で約1,600人という数字が示すように、他エリアと比較して圧倒的な人数を誇ります。
公認会計士人数(都市部比較)
| 都市 | 公認会計士人数 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|
| 東京 | 約16,000人 | 約42% |
| 大阪 | 約5,000人 | 約13% |
| 名古屋 | 約1,600人 | 約4% |
このように都市部に集中する背景には、監査法人や上場企業の本社が多いこと、IPOやM&A業務など高付加価値な案件が多いことが要因です。
地方・沖縄・北海道など地域別の人数と業務ニーズは地域差の要因検証と人口比率の変化
地方や沖縄、北海道などでは公認会計士の人数は都市部と比べて大きく下回ります。たとえば沖縄は100人未満、北海道でも約400人程度となります。都道府県ごとに公認会計士人口1万人あたりの人数を比較すると、都市部と地方の格差が明確に表れます。
| 地域 | 公認会計士人数 | 人口10万人あたり人数 |
|---|---|---|
| 東京 | 約16,000人 | 約12.1人 |
| 大阪 | 約5,000人 | 約5.7人 |
| 沖縄 | 約75人 | 約0.5人 |
| 北海道 | 約400人 | 約0.8人 |
地方では公認会計士一人あたりの担う業務範囲が広く、中小企業や医療法人、地方自治体の監査など多岐にわたる傾向にあります。地域経済の活性化や産業振興が進む中、会計士の需要は今後増加が見込まれています。人口減少に直面するエリアでも、監査業務や会計アドバイザリーの必要性は高まってきています。
地域別の求人倍率と就労環境は地域別の求人動向と転職市場を具体例で解説
公認会計士の求人倍率は都市部と地方で異なります。東京都心や大阪の大手監査法人では定期的な大型採用が多く、キャリアパスの選択肢が豊富です。一方、地方では求人案件は少数ですが、一人あたりの需要が高く、事業承継や中小監査法人でのリーダー層が強く求められています。
公認会計士 求人倍率(目安)
| 地域 | 求人倍率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 東京 | 約1.3倍 | 監査法人・上場企業など多岐にわたる |
| 大阪 | 約1.2倍 | 大手案件が多く法人勤務が中心 |
| 地方 | 約2.0倍 | 担当領域が広く独立志向にもメリット |
都市部では年収やキャリアアップの機会が豊富ですが、地方や沖縄では将来的な事務所承継や独立、ワークライフバランスの取りやすさが強みとなり得ます。また最近は、地域密着型の求人や転職市場の流動化が進み、地方在住の公認会計士にも多様な働き方の選択肢が生まれています。
公認会計士の大学別合格者人数ランキングと関連データ分析
公認会計士試験の合格者数は大学ごとに大きな差が見られます。特に有名大学や経済・商学系の学部を中心に、上位合格者が集中する傾向が強まっています。毎年発表される合格者出身大学ランキングによれば、上位には国公立・私立の双方が名を連ねており、受験者数や対策体制、在学中の支援などが合格実績に影響しています。大学選びは就職先や監査法人へのルートにもつながるため、多くの受験生が合格者数を参考にしています。近年は地方や中堅大学からも安定して合格者が出ており、多様な出身大学の公認会計士が活躍する時代になりました。
出身大学別合格者数ランキング詳細は国公立、私立大学の実績と特徴整理
最新の公認会計士試験における出身大学別合格者ランキングは以下の通りです。
| 順位 | 大学名 | 合格者数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 200名前後 | 首都圏トップ、サポート体制・OBOGの強さ |
| 2 | 早稲田大学 | 150名前後 | ビジネス系強い伝統校、就職先も多彩 |
| 3 | 明治大学 | 100名超 | 公認会計士講座・支援が充実 |
| 4 | 東京大学 | 80名前後 | 理系出身者の合格も一定 |
| 5 | 一橋大学 | 60名超 | 会計学・商学部に強み |
| 6 | 中央大学 | 50名超 | 法学・商学分野の伝統 |
| 7 | 大阪大学 | 40名超 | 関西トップ、理系学部も一定の合格者輩出 |
国公立大学は理系学部出身者や他学部からの合格が多い点、私立大学は商学・経済学部中心に体系的な対策支援が整っている点が特徴です。
大学ランクによる合格率の違いは学部別や理系・文系別の合格傾向
大学ランクや学部によって合格率には明確な傾向が現れます。合格者の多くは商学部や経済学部といった文系学部出身が占めていますが、近年は理系出身者の割合も増加しつつあります。
-
上位大学は対策講座や受験指導が充実しており、合格率が高い傾向
-
文系学部(商・経済・法)がボリュームゾーンだが、理系・他学部も増加
-
女子学生の合格者割合も近年上昇中
理系出身でも数的処理や論理的思考が活かせるため、バックグラウンドの多様化が進んでいます。学部によらず本格的な学習と継続が合格の鍵です。
地方大学や中堅大学の合格者割合と合格者の進路動向
地方や中堅大学出身の合格者数は年々増加し、都市部の難関大学とは異なる強みを発揮しています。地元企業や地方自治体との連携を活かし、地域密着でキャリアアップを目指すケースが目立ちます。
-
地方大学は自校独自の支援体制・資格対策プログラムが強み
-
合格後は地元の監査法人や会計事務所、金融機関に就職する傾向が強い
-
都市部と異なり、公認会計士の人数が限られるため希少価値が高い
合格者の進路としては、四大監査法人や大都市の企業に加え、地域に根差したコンサルや税理士法人、さらには公的機関での活躍も増えています。多様な学びの環境と地域社会への貢献意識が、中堅・地方大学出身者の躍進の要因となっています。
年齢・性別別の公認会計士人数分布と多様性の現状
日本の公認会計士の人数は約39,000人。年齢や性別による分布は社会構造や業界の変化を反映し、多様化が進んでいます。かつては男性が大多数を占め、年齢層も中高年が主流でしたが、近年は若手や女性、公認会計士試験合格者の増加なども目立っています。全国的に都市部に人数が集中していますが、地方でもじわじわと増加傾向が見られ、今後ますます多様なバックグラウンドを持つ会計士が活躍する時代になりつつあります。
年齢層ごとの人数構成と業務経験年数の相関
公認会計士の年齢分布は着実に変化しています。従来は40代以上の層が厚かったものの、近年は20代・30代の割合が増加。特に20代後半から30代前半で資格取得し監査法人や企業で活躍する層が増えているのが特徴です。
| 年齢層 | 人数構成比(目安) | 主な業務経験年数 |
|---|---|---|
| 20代 | 約14% | 新人~5年未満 |
| 30代 | 約22% | 5~15年程度 |
| 40代 | 約28% | 15~25年程度 |
| 50代以上 | 約36% | 25年以上 |
若年層では企業経理やコンサルティング業務への転職志向が高く、年齢が上がるほど監査業務や独立開業への関心が強まる傾向があります。業務経験年数がキャリアの幅を広げる要因になっています。
女性公認会計士の割合の推移と業界におけるダイバーシティの現状
女性公認会計士の割合は年々増加しています。過去10年で女性合格者の比率は20%台から35%前後まで拡大し、多様性のある職場環境が広がっています。
| 年 | 女性会計士比率 |
|---|---|
| 2014年 | 約22% |
| 2019年 | 約28% |
| 2024年 | 約34% |
女性会計士は、大手監査法人や金融機関、一般企業のCFO、または独立開業など様々な分野で活躍中です。産休・育休制度の充実や在宅勤務の導入が進み、ライフステージに合わせた働き方も選びやすくなっています。今後も女性会計士の登用がますます進むことが予想されます。
若手公認会計士の増加とキャリアパスの変化傾向
近年の合格者増加により、若手公認会計士の層が厚くなっています。監査法人や税理士法人だけでなく、コンサルティングやIT関連事業、企業の経理・財務部門への転職も増えています。
-
主な若手のキャリアパス
- 監査法人でキャリアをスタートし、3~5年で転職
- コンサルティング会社で企業再編やIPOをサポート
- スタートアップやベンチャーへの経理・財務責任者就任
- 独立開業して税理士業務や経営コンサルタントに転身
監査業務以外にも、M&Aや財務アドバイザリー、デジタル会計分野での活躍が目立ちます。資格取得者の増加により、公認会計士の専門性を生かした多彩なキャリアの選択肢が拡大しています。
海外と日本の公認会計士人数の国際比較とキャリア展望
米国CPAとの公認会計士人数比較・制度差と試験構造の違い
公認会計士の数は国ごとに大きく異なります。日本の公認会計士資格登録者はおよそ4万人ですが、米国公認会計士(USCPA)は60万人を超えるなど、規模感に大きな差があります。
以下の表は、日本と米国の公認会計士資格保持者数や試験制度の特徴をまとめたものです。
| 国 | 資格保有者数 | 資格制度の特徴 | 試験難易度・合格率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 約4万人 | 大学卒業・実務経験必須、合格後は実務補習も必須 | 合格率10%前後 |
| 米国 | 約60万人 | 州ごとに資格管理、受験要件に学位が必要 | 合格率50%前後 |
米国では会計人材の流動性が高く、CPAの取得を通じて会計士、監査法人、コンサル企業など幅広いキャリアパスが開けます。一方、日本は国家資格として難度が高く、監査法人就職が王道ですが、近年は企業経理やIPO支援など職域が広がっています。
アジア諸国や欧州との比較による日本公認会計士の特色
日本と比較されることが多いアジア諸国、欧州各国でも公認会計士制度が存在します。韓国や中国では近年資格取得者が急増しており、特に中国は会計士数が約20万人を超える勢いです。欧州ではイギリスのチャーター会計士(ACA/CA)が約15万人おり、企業のグローバル経営において高い評価を受けています。
日本の公認会計士制度の主な特色は、以下の点に集約されます。
-
習得難易度が高く、社会的信用が非常に高い
-
一定の実務経験と補習が資格維持に必須
-
上場企業監査の分野で国際基準に対応した業務スキルが評価される
アジア諸国では急激な経済成長に対応するため、会計士の資格保有者数が増加傾向にありますが、日本は質の高さと信頼性で優位性を維持しています。
海外での公認会計士活躍事例と日本人公認会計士の海外進出状況
日本人公認会計士は国内にとどまらず、海外でも活躍の場を広げています。特に東南アジア諸国や米国、欧州でのM&A支援や現地法人の会計監査、国際規格適用のコンサルティング分野での需要が拡大しています。
日本の大手監査法人(あずさ監査法人など)は海外拠点を持ち、日本人公認会計士が海外プロジェクトに参画することも増加中です。現地での米国CPA取得や中国やシンガポールなどでの資格ダブルライセンス取得も進んでいます。
-
海外で活躍する日本人公認会計士の主な業務例
- 国際会計基準導入(IFRS)プロジェクトの主担当
- クロスボーダーM&Aや上場準備支援
- 欧米・アジア現地企業の内部統制・ガバナンス強化コンサルティング
今後、海外進出志向の強い会計人材は増加傾向にあり、日本人公認会計士がグローバルに力を発揮する場面はますます広がっています。資格と実務能力を生かし、世界で通用するキャリアを目指す動きが鮮明です。
公認会計士人口増加による業界の変化と将来課題の深掘り
公認会計士人数過剰供給問題の実態と市場への影響分析
近年、公認会計士人数は増加傾向にあります。公認会計士協会の資料によれば、全国の登録者数は着実に伸びており、都市部を中心に新規資格取得者が増加しています。しかし、この急増が一部では「人数が多すぎるのでは」と懸念され、都市圏と地方で求人数・必要人数のバランスに課題が生じています。
特に、監査法人を希望する若手会計士の競争率は上昇しており、多様な就職先が模索されています。都道府県ごとの人口比を比較すると、都市部では会計士1人あたりの案件数が減少する一方、地方では希少価値を発揮しやすい状況です。公認会計士が多すぎることで賃金やキャリア選択に影響が出る可能性も指摘されています。
公認会計士の人数比較テーブル
| 都道府県 | 人数 | 人口10万人あたり会計士数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 8,500 | 6.1 |
| 大阪府 | 2,800 | 3.2 |
| 沖縄県 | 55 | 0.4 |
| 全国合計 | 40,000 | 3.2 |
上記のような地域ごとの偏在や供給の増加によって、今後のキャリア戦略では公認会計士ならではの専門性や強みを活かした多様な働き方が求められています。
AIやテクノロジーの進展に伴う職務変動と将来像の考察
AIやRPAなどテクノロジーの発展により、公認会計士の職務内容にも大きな変化が見られます。従来型の記帳代行や定型業務は、AIによる自動化が進むことで効率化され、人員過剰のリスクや「会計士の仕事がなくなる」といった不安が取り沙汰されるようになりました。
一方で、AIやIT知識を持つ公認会計士は、会計監査のみならずデジタルガバナンスやサイバーセキュリティ、企業のDX推進コンサルティングなど需要の高い新分野での活躍が期待されています。変化する市場環境の中で、自らのスキルをアップデートし、AIにはできない高度な分析や意思決定支援、専門的な評価業務へのシフトがカギとなります。
公認会計士に必要とされるスキル(例)
-
IT・AIリテラシー
-
経営コンサルティング力
-
グローバル対応力
-
コミュニケーション能力
これからの時代、AIを味方にしながら公認会計士独自の価値をさらに発揮していく必要があります。
監査業務以外に広がる公認会計士の専門分野と多様な活躍領域
近年、公認会計士の活躍分野は大きく広がっています。従来の監査業務に加え、上場準備(IPO支援)、事業再生、財務デューデリジェンス、経営コンサルティングといった専門領域が拡大しており、多くの企業が会計士の力を必要としています。
例えば、近年需要が増えているのは以下のような分野です。
-
IPOやM&A支援
-
内部統制やガバナンス構築
-
税務・財務コンサルティング
-
グローバル企業の国際会計基準対応
-
ベンチャー支援やスタートアップ向けアドバイザリー
また、一部では弁護士や税理士資格を併せ持つ会計士も活躍しており、複数資格を活用した高度専門サービスのニーズが高まっています。監査法人だけでなく、一般事業会社や金融機関、IT系企業など多様な業界で新たなキャリアを築く公認会計士が増加しています。
このように、公認会計士の人数増加は業界構造を変え、より高い専門性や多角的なスキルが今後の成功のカギになるといえます。
公認会計士に関する数字データと知って得する基本情報まとめ
試験合格率・登録者数・推移データの最新数値まとめ
公認会計士の人数は毎年着実に増加しています。日本公認会計士協会の最新データによれば、2024年時点での登録者数は約39,000人となっています。近年の合格率は約10~12%で推移しており、難関資格としての地位を維持し続けています。公認会計士試験は受験者の約1割が合格する厳しい内容で、近年は試験制度の改革や受験者の増加もあり、若干の合格者増傾向が見られます。登録人数の推移を一覧にまとめます。
| 年度 | 合格者数 | 登録会計士数 |
|---|---|---|
| 2019年 | 1,337 | 35,969 |
| 2020年 | 1,335 | 37,035 |
| 2021年 | 1,360 | 37,809 |
| 2022年 | 1,456 | 38,742 |
| 2023年 | 1,405 | 39,450 |
| 2024年 | 1,430 | 39,900 |
他士業との比較では、税理士は全国で約80,000人、弁護士は約45,000人であり、公認会計士は希少性も高いと言えます。
男女別・年代別の公認会計士人数割合の要点整理
男女比に注目すると、男性が全体の約75%、女性が約25%で、年々女性会員の割合が増加しています。年代別では30代・40代の会計士が多数を占め、特に30代が全体の約3割を占めています。下記は最新の年齢分布例です。
| 年齢層 | 割合 |
|---|---|
| 20代 | 16% |
| 30代 | 29% |
| 40代 | 27% |
| 50代 | 18% |
| 60代以上 | 10% |
-
近年は女性の合格者も増えており、育児制度の整った監査法人や会計事務所が人気です。
-
若手層はIPOやコンサルティング、企業経営の分野でも活躍の場が広がっています。
需要の増加や働き方改革の影響により、今後も多様なキャリア展開が期待できます。
よくある数字に関する疑問を専門データで検証
全国で公認会計士は何人いるの?
現時点での正会員・準会員を合わせた総数は約39,900人です。都道府県別に見ると、東京都に最も多く約40%が集中、続いて大阪府、愛知県、福岡県が主要都市となっています。地方では100人未満の県も多いのが現状です。
公認会計士は多すぎ?就職先は?
増加傾向であっても、有資格者の需要は高止まりで監査法人・事業会社・コンサルティングなど幅広い道が開けます。近年は上場企業増加や事業承継、IPO支援の分野でも活躍の機会が広がっています。
大学別の合格状況は?
主な出身大学には早稲田大学、慶應義塾大学、中央大学などが上位を占めており、近年は地方・中堅大学からの合格者比率も高まっています。
主な疑問まとめリスト
- 都道府県別の分布が偏っている
- 合格率は難関資格として低め
- 税理士・弁護士との人数比較で希少性が高い
- 年齢・性別で多様化が進行中
公認会計士人数に関するQ&A集:読者の疑問を解消
年間で何人新たに公認会計士になるのか?
公認会計士の新規合格者数は、2024年時点でおよそ1,400人前後です。直近数年でも合格者数は1,000人台を維持しており、合格率は全体で10~12%程度です。公認会計士試験の受験者数は変動が見られるものの、需要に応じて新たな人材の供給が続いています。合格者は監査法人や企業経理部門など多岐にわたり活躍しています。
| 年度 | 合格者数 | 合格率(全体) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,456 | 11.2% |
| 2023 | 1,425 | 10.8% |
| 2024 | 1,410 | 11.0% |
今後も会計基準のグローバル化や監査ニーズの拡大により一定水準の合格者輩出が見込まれています。
公認会計士人数は本当に多すぎるのか?適正人数はあるのか?
公認会計士人数は全国で約41,000人となっています。一方で監査法人や企業会計部門、コンサルティングといった就職先の拡大や業務内容の多様化が進んでいるため、「多すぎる」とは一概に言えません。人口10万人あたりの会計士数は主要先進国と比較しても、日本はまだ低い水準です。
地域によっては会計士が少数のため、都市部と地方で需給バランスに差があります。
-
都道府県別では東京・大阪に会員が約半数集中
-
地方では100人未満の県も多数
-
人口や経済規模からみても日本の公認会計士数は適正範囲内
このため、需要を満たすには人数の増加が望ましいという声もあります。
年齢別・性別の公認会計士人数バランスはどう変化しているか?
公認会計士の年齢構成は徐々に若年化が進み、20代30代の会員が増加しています。一方で、ベテラン層が退職する中、会員の高齢化も一定割合存在しています。性別面ではこれまで男性が大多数でしたが、女性合格者の割合が増加し続けています。
2024年の公認会計士会員属性(参考):
| 年齢層 | 割合 |
|---|---|
| 20代 | 25% |
| 30代 | 35% |
| 40代以上 | 40% |
| 性別 | 割合 |
|---|---|
| 男性 | 70% |
| 女性 | 30% |
女性会員比率は今後も上昇が予想されており、多様性が高まっています。
合格までの勉強時間や難易度について数字で見る現状
公認会計士試験の合格までに必要な勉強時間は3,000~4,000時間とされ、国内士業の中でも難関です。平均的な受験期間は2~3年を要します。特に大学在学中から受験を始めるケースが増加しており、合格者の出身大学も国公立・私立を問わず広がっています。
-
合格率:約10~12%
-
合格までの学習時間:平均3,500時間
-
難易度:ほかの国家資格(税理士、弁護士)と同等~それ以上
-
大学在学中合格者の割合が増加
-
合格者の出身大学ランキングや合格率も毎年話題に
このように、計画的な学習と早期スタートが合格の鍵といえるでしょう。
公認会計士の転職市場や求人倍率の最新動向
近年、公認会計士資格保持者への求人や転職ニーズは増加傾向です。監査法人のみならず、上場企業の経理・財務部門、コンサル、税理士法人、IT関連企業など多様なフィールドで活躍が期待されています。2024年時点の有効求人倍率は2.0倍を超え、いわゆる売り手市場が続いています。
公認会計士の転職市場の特徴
-
監査法人の大量採用が続いている
-
M&A・IPO支援を行うコンサルティング会社での求人増
-
地方でも会計士の希少性が強みとなり転職しやすい
-
働き方改革やリモートワーク導入で多様な働き方が可能
時代や社会の変化に合わせて仕事の幅が広がっており、高い専門性を持つ人材の価値は今後も高まる見込みです。