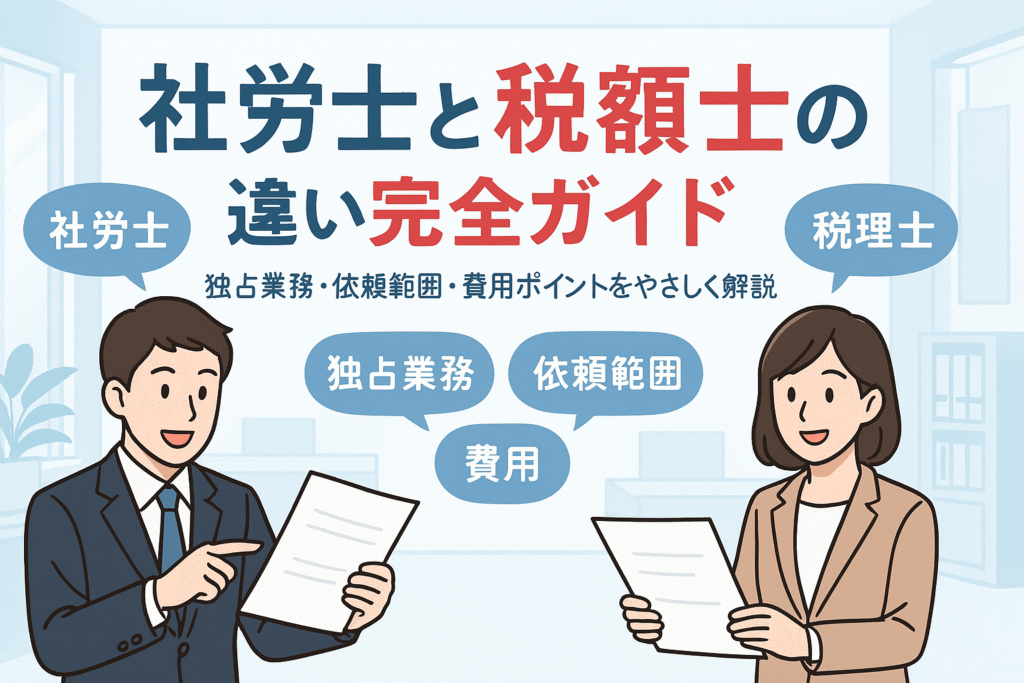「社労士と税理士、どっちに何を頼めばいいの?」──給与計算と年末調整の線引き、就業規則や記帳の担当、費用の相場まで迷いがちですよね。実務では、年末調整は税務申告に直結し、給与計算は労務運用の影響が大きいなど“正しい分担”が成果とコストを左右します。本記事は独占業務の境界と依頼範囲を一目で把握できる全体マップで、失敗しない使い分けを提示します。
例えば、税理士は確定申告・消費税対応・税務調査立会い、社労士は社会保険の新規適用・入退社手続・就業規則整備・助成金対応が得意領域です。合格率の目安は社労士約5~7%程度、税理士(官報合格ベース)では一桁台が一般的で、専門性の違いが実務にも反映されます。
顧問とスポットの使い分け、会社設立時の税務設計や役員報酬、グレーゾーンの賢い対処、見積もりチェックリストまで具体例で解説します。今日の悩みを、明日の運用改善につなげましょう。
社労士と税理士の違いがすぐわかる!独占業務と依頼範囲の全体マップ
独占業務を見抜く依頼のベストな分け方
企業が迷いやすいのは、どの業務を誰に任せるかという線引きです。社労士は労働社会保険の手続きや労務相談を担当し、税理士は税務代理や税務書類の作成、会計に関するアドバイスを担当します。独占業務の観点が鍵で、税務代理・申告書作成は税理士の独占業務、社会保険・労働保険の手続代行は社労士の独占業務です。例えば、会社設立後の税務署届出や消費税の申告は税理士、雇用保険の適用・月額変更や算定基礎届の提出は社労士に依頼するのが妥当です。グレーに見えても、目的で見極めると判断しやすくなります。目的が税金の計算・申告に接続すれば税理士、従業員と会社の労務運用に接続すれば社労士という整理で、窓口を素早く決められます。
-
税理士向きの例: 申告書作成、税務調査対応、節税相談、記帳指導
-
社労士向きの例: 社会保険の新規適用と算定、就業規則の作成・改定、助成金手続き
補足として、両者が連携することで手戻りやリスクを減らせます。
給与計算と年末調整はこう違う!実務でのスマートな線引き術
給与計算と年末調整はセットで語られがちですが、性質が異なります。給与計算は勤怠や賃金ルールに基づく処理で、残業計算や社会保険料の控除設定など労務運用が中心です。就業規則や36協定との整合、休職・復職対応など人事実務と強く結びつくため、社労士の守備範囲になりやすいです。一方、年末調整は源泉徴収・住宅ローン控除・配偶者控除など税額計算や法定調書の作成といった税務処理が中心で、税理士の力量が問われます。どちらもシステム連携が進んでいますが、誤りが生じるポイントは異なります。労務規程の適用判断が絡む部分は社労士、税額計算や控除適用の判定は税理士と分担すると、ミスの連鎖を防げます。実務では、毎月の給与計算は社労士、年末の控除計算や源泉徴収票・法定調書作成は税理士という体制が合理的です。
| 業務 | 主眼 | 主な判断ポイント | 推奨窓口 |
|---|---|---|---|
| 給与計算 | 労務運用 | 勤怠・割増・社会保険料 | 社労士 |
| 年末調整 | 税務計算 | 控除適用・源泉精算 | 税理士 |
| 法定調書 | 税務提出物 | 支払調書・合計表 | 税理士 |
テーブルのとおり、目的と判断ポイントで迷いを解消できます。
記帳業務や就業規則などグレーゾーンの賢い対処法
グレーに見える領域ほど、先に「最終目的」と「独占業務」を確認すると迷いません。記帳は会計処理の正確性と税務申告の前工程であるため税理士に依頼するのが基本です。逆に、就業規則は労働条件の明確化や労務リスクの抑制が主目的で、社労士が法令適合や実務運用まで見据えて設計します。助成金は申請要件が労務運用と直結し、社労士が向いています。実務のステップは次の通りです。
- 目的を言語化する(税額計算に直結か、労務運用の是正か)
- 独占業務に抵触しないか確認する(申告や手続代行の可否)
- 原票の所在を整理する(会計帳簿なら税務、勤怠・賃金台帳なら労務)
- 連携計画を決める(データ授受、チェック範囲、期限)
- 責任分界点を文書化する(誰がどの判断をするかを明確化)
この流れで進めると、重複作業の削減と法令違反の回避が両立しやすくなります。社労士 税理士の連携体制を整えることで、税務と労務の境界で起こりがちな抜け漏れを抑えられます。
社労士に頼むと成功しやすい!費用・相場で選ぶ依頼パターンまるわかり
今すぐ依頼すべき社労士が得意なテーマと最適な範囲
創業や採用が動くタイミングは、社労士への依頼でつまずきを防げます。社会保険の新規適用や従業員の入退社手続き、就業規則の整備、助成金の活用は、独占業務や実務経験がものを言う領域です。とくに給与計算や労働保険の年度更新は税務との整合も重要で、社労士と税理士が連携するとミスと手戻りを大幅削減できます。以下のように範囲を決めると費用対効果が高まります。
-
新規適用・入退社は申請と帳票の整備まで一括依頼
-
就業規則は現状把握から運用ルールの策定まで包括依頼
-
助成金は要件判定、計画届、支給申請までフルサポート
社労士は労務、税理士は税務が専門です。両方が必要な局面では、窓口を一本化しつつ役割を明確化するとスムーズです。
顧問契約とスポット依頼の違いで費用を無駄なく!
スポットで済む手続きもあれば、日常の相談が多い企業は顧問の方が結果的に安くなります。相場感は地域や規模で変動しますが、考え方の基準を押さえると判断しやすくなります。
| 依頼形態 | 向いているケース | 目安の範囲 | メリット |
|---|---|---|---|
| 顧問契約 | 従業員数が増加、相談が頻繁 | 相談、手続きの定例化、是正対応 | 毎月のコストが読めて迅速対応 |
| スポット | 創業時や単発の手続き中心 | 新規適用、入退社、就業規則改定、助成金申請 | 必要時のみ発注で費用最小化 |
無駄を減らす手順は次の通りです。
- 月あたりの相談回数と手続き件数を定量化する
- 年間コストで顧問とスポットを比較する
- 税務・会計の変更点が多い年は、社労士と税理士の連携プランを選ぶ
- 6か月後に運用を見直し、契約形態を最適化する
ルール作りから運用定着までをセットで考えると、労務トラブルの予防とコスト管理が両立します。
税理士に任せて節税・決算を強化!効果絶大な業務の整理術
本当に税理士に任せたい業務と納期管理のコツ
決算や消費税、税務調査は失敗が許されない領域です。税理士に任せるべき中心業務は、法人税等の申告書作成、消費税のインボイス・適格請求書対応、税務調査の立ち会いと是正案の提示、そして記帳指導や会計処理の整備です。特に独占業務である税務代理や税務書類の作成は専門性が高く、プロの関与でペナルティと機会損失を抑えられます。納期管理は、月次を締めてから決算作業までの逆算スケジュールが鍵です。社労士と連携した給与・賞与データの確定、労務起因の費用計上の調整、会社の承認フローの短縮を事前に設計し、申告期限前の想定納税額の提示で資金手当てを円滑にします。次の4点を押さえると精度が上がります。
-
月次試算表の5営業日提出で誤差を早期発見
-
消費税の簡易か原則の見直しを毎期チェック
-
固定資産の耐用年数と税法の差異を一覧で管理
-
税務調査の質問事項想定集を平時から更新
短期の負荷を下げるため、記帳は会計事務所のルールに合わせて統一フォーマットに寄せるとコミュニケーションコストが下がります。
スポット相談が輝く!会社設立や報酬設計のウラ技活用術
設立や役員報酬は初期の一手で数年の税負担が変わります。税理士へのスポット相談は、定型顧問に加えて高インパクト領域に絞ると費用対効果が高いです。会社設立では資本金、事業年度、消費税の課税事業者選択、税務署等への届出書の選択を同時に検討します。役員報酬は改定可能時期と損金算入の要件を守りつつ、家族への給与や賞与、退職金も含めた生涯の税負担で設計します。資金繰りと節税は以下の手順が実践的です。
- 黒字化時期のシナリオを3本用意し納税額を試算
- 設備投資や助成金の時期調整で税額とキャッシュを最適化
- 消費税の還付可否を踏まえ仕入と支払サイトを調整
- 金融機関向けの計画書と実績管理を単一指標で統一
- 社労士と連携し助成金・労働保険の手続きを同歩
スポットの積み上げで十分な場合もあれば、相続や組織再編のように継続支援が必要な場面もあります。社労士と税理士を適材適所で使い分けると、税務と労務の両面でリスクを最小化できます。
年末調整と給与計算で社労士と税理士を賢く使いこなす方法
年末調整のメイン担当は誰?分担の決め方ガイド
年末調整は「税務の最終計算」と「労務データの精査」が交差します。社内の実務では、源泉徴収票の作成や控除証明の確認、保険料控除や住宅ローン控除の適用など、税務計算は税理士の得意領域です。一方で、扶養や給与、社会保険の資格取得・喪失、育休や賞与の取扱いなど、従業員情報の正確性を担保する前段のデータ整備は社労士が強みです。判断軸は三つです。第一に、会計ソフトと給与計算ソフトの連携状況です。連携が弱ければ社労士が前処理、税理士が最終計算という分担が安全です。第二に、外部委託の範囲です。給与計算を社労士に委託しているなら、年末調整の資料整備も社労士が主担当にし、税額計算や法定調書合計表、支払調書の作成・提出は税理士が担当します。第三に、社内体制の監査性です。入力と承認を分離し、税務署提出物は税理士、公的保険の修正は社労士が担当するなど、独占業務とリスクの所在で線引きするとミスと責任の所在が明瞭になります。
-
社労士は労務データの正確性担保と控除資格の確認が強み
-
税理士は税額計算・法定調書・源泉徴収票の整合性確認が強み
-
会計と給与のデータ連携度合いでメイン担当を決める
補足として、繁忙期の問い合わせ窓口は一本化し、実務は社労士と税理士で分業すると従業員対応の品質が安定します。
給与計算の属人化STOP!効率化できる運用ルール
給与計算は「入力の標準化」「変更点の二重チェック」「締日運用の厳格化」で属人化を断ち切れます。まず、マスタと月次の入力区分を分け、固定項目はマスタ管理、変動項目は月次ファイルに限定します。次に、差分管理を徹底します。前月比で賃金・手当・控除・社会保険料が±5%超ならアラート、入退社・等級変更・資格取得喪失は証憑添付を必須にします。最後に、監査フローです。社内一次、社労士の労務監査、税理士の税務監査の三段階で、支給総額と源泉所得税、住民税、社会保険料のクロスチェックを行います。
| 運用ルール | 目的 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| マスタ凍結日を設定 | 直前改定でのミス防止 | 締日3営業日前にロック |
| 差分レポート自動出力 | 異常検知の強化 | 前月比・前年同月比を併記 |
| 承認権限の分離 | 不正防止 | 入力者と承認者を分ける |
| 証憑必須化 | 根拠の明確化 | 手当新設・等級改定は添付 |
| リハーサル計算 | 本番前の検証 | 本計算の2日前に実施 |
-
源泉税・社会保険の整合は税理士と社労士のダブルチェックが最も効果的
-
勤怠締めと給与締めのズレを最小化し、残業計算の確定基準を明文化
この仕組み化で時間のブレが減り、会計事務所や社労士事務の負荷分散にもつながります。
税理士と社労士はどっちが難しい?学習時間・合格率でズバリ比較
受験資格や試験の違いをやさしく解説
税理士と社労士の難易度は「試験制度」と「受験資格」の違いを押さえると見えてきます。税理士は科目合格制で、会計と税法の計5科目に合格すれば最終合格です。毎年2~3科目ずつ受けるなど計画が立てやすく、長期戦になりやすいのが特徴です。一方で、社労士は年1回の本試験で選択式と択一式を同日に受ける一発勝負です。範囲は労働法や社会保険法など広く、横断的な知識整理が鍵となります。受験資格にも差があり、税理士は会計・法律系の学歴や実務要件が必要、社労士は学歴要件や実務経験など複数のルートがあります。つまり、税理士は長期継続、社労士は一発集中が基本の学習戦略です。どちらも独占業務があるため、将来の働き方や業務内容をイメージして選ぶのが失敗しないコツです。
-
ポイント
- 税理士は科目合格制で計画的に攻められる
- 社労士は年1回の一発勝負で総合力が問われる
- 受験資格の要件が異なるため事前確認が重要
合格までの平均学習時間・合格率を徹底比較!準備のポイントも解説
難易度を測る目安として、学習時間と合格率のレンジを比較します。一般的に、社労士は800~1,000時間前後が目安で合格率は毎年一桁台です。広範囲のインプットと過去問演習をバランスよく回す必要があり、直前期の得点調整が勝負どころです。税理士は総計で2,000~3,000時間以上になりやすく、科目別の合格率は概ね1~2割台ですが、全5科目の最終到達には複数年を要する受験生が多いです。準備の要点は、税理士なら出題頻度の高い論点を科目ごとに計画的に積み上げ、社労士なら横断整理と法改正対応を早めに習慣化すること。いずれも模試の活用と復習のPDCAが合否の分水嶺です。以下の比較で学習計画の起点を固めてください。
| 比較項目 | 社労士 | 税理士 |
|---|---|---|
| 試験方式 | 年1回、一発勝負 | 科目合格制、複数年可 |
| 目安学習時間 | 800~1,000時間 | 2,000~3,000時間以上 |
| 合格率の傾向 | 毎年一桁台 | 科目ごと1~2割台 |
| 学習の肝 | 横断整理と法改正対応 | 科目ごとの計画的積上げ |
| 向くタイプ | 集中力と総合力重視 | 継続力と粘り強さ重視 |
- 受験要件を確認して着手時期を決める
- 学習時間の確保を先にカレンダーへブロックする
- 過去問と模試を主軸に弱点補強をルーチン化する
- 直前期の戦略を早期に設計して得点源を固定する
上記を踏まえると、短期集中が得意なら社労士、長期で積み上げられるなら税理士が合う傾向です。どちらも独占業務と将来性を見据えた計画づくりが合格への近道です。
社労士と税理士の年収レンジ&働き方を徹底比較!独立vs事務所勤務のリアル
年収が大きく変わる!要因を事例でわかりやすく解説
年収は「何をどれだけ、誰に売るか」で決まります。社労士は労務相談や社会保険手続き、給与計算を顧問契約で積み上げ、税理士は記帳代行から申告、税務相談、節税提案までの税務を継続顧問で拡大します。共通するカギは、顧問数と単価、地域の相場、事務所規模、そしてダブルライセンスの有無です。たとえば単価が同水準でも、都市部は顧客の業種が多様で追加依頼が生まれやすく、結果として年収が上振れしやすいです。逆に地方でも紹介ネットワークが強ければ安定収益が見込めます。社労士と税理士を比較すると、税務代理という独占業務の単価が効きやすく、税理士は高単価案件の比率が上がりやすい点が特徴です。いずれの資格でも、継続性の高い顧問とスポットのバランスを設計し、単価改定やサービス拡張で生産性を高めることが年収の分岐点になります。
-
顧問契約数が増えるほど固定収益が安定しやすい
-
地域の相場と顧客の業種構成が単価に直結する
-
ダブルライセンスで付加価値が上がりクロスセルが進む
補足として、紹介経路の多様化やオンライン相談の活用は、地域差を埋める有効な手段になります。
| 比較軸 | 社労士の傾向 | 税理士の傾向 |
|---|---|---|
| 主要収益 | 労務顧問、手続き代行、給与計算 | 顧問料、申告報酬、決算、相続 |
| 単価形成 | 従業員数×手続き件数×相談頻度 | 売上規模×取引数×決算難易度 |
| 伸ばし方 | 就業規則や助成金などの追加提案 | 節税提案、組織再編、資金繰り支援 |
| 地域差の影響 | 従業員数の多い企業群で優位 | 事業者数と案件難度で優位 |
| ダブルライセンス効果 | 労務×税務で一気通貫対応が可能 | 税務窓口から労務課題の受注が可能 |
テーブルの通り、税務は決算・申告の節目で高単価化しやすく、労務は通年の相談頻度で積み上げるモデルになりやすいです。
独立開業と事務所勤務のキャリアのチャンスとリスク
独立は裁量が最大化し、価格設定やサービス設計を自分で決められます。一方で営業、採用、教育、品質管理、IT投資まで全責任を負うため、キャッシュフローの管理や繁忙期の人員調整がリスクです。事務所勤務は教育体制やレビューで品質を担保しやすく、税理士事務所や社労士事務所での経験が実務力を底上げします。昇給は評価制度、担当件数、難易度、付加価値提案で決まりやすく、専門特化で単価テーブルの上位を狙えます。社労士と税理士のどちらでも、開業初期は顧問の積み上げが肝で、固定費の設計と業務効率化が勝敗を分けます。ダブルライセンスは独立・勤務どちらでも武器になり、クロスセルでLTVを押し上げます。将来の独立を見据えるなら、勤務中に営業の型と原価管理を学び、再現性のある集客チャネルを作ることが重要です。
- 勤務で実務と営業の型を蓄積する
- 固定費を抑えたスモールスタートで独立する
- 標準化とITで一人当たり生産性を高める
- 顧問の解約率を下げる仕組みを整える
- 強み分野を明確化し単価を段階的に引き上げる
番号の流れに沿って準備すると、独立後の不確実性を抑えつつ年収の上振れ余地を確保しやすくなります。
ダブルライセンスの力!社労士と税理士で広がる実務の連携術
連携で実現する業務範囲拡大と信頼性アップのメリット
労務の現場で起きる意思決定は、税務とつながっています。例えば人事制度の見直しや賃金設計は社会保険料や所得税に波及し、逆に節税策は雇用や就業規則の運用に影響します。社労士と税理士が連携すると、労務リスクの低減と税務最適化を同時に設計でき、企業の実務は一気に滑らかになります。さらに、独占業務を法令順守で分担することで、不適切な手続きや申告のやり直しを防げます。継続顧問では、労働保険や社会保険の手続き、給与計算、税務申告、記帳代行までを一体運用し、情報の二重入力や計算ミスを削減できます。IPO準備や助成金・補助金活用でも、人件費計上や要件確認を一気通貫で支援でき、経営の意思決定スピードを高められます。
-
労務×税務の同時最適化で手戻りとコストを抑制
-
独占業務の分担により法令違反リスクを回避
-
情報連携の標準化で処理時間と計算ミスを削減
補足として、社内ルールと会計処理の整合が取れるほど、監査対応や調査時の説明コストが下がります。
ダブルライセンス取得の最適な順序&実務経験の積み方
社労士と税理士を目指す順番は、実務で触れるデータの多さと学習継続のしやすさで決めるのが現実的です。人事・総務に近い環境なら社労士先行が有利で、就業規則、労働保険、社会保険の運用を押さえつつ、給与計算と年末調整の接点で税務の素地を作れます。会計事務所や経理に近いなら税理士先行が合理的で、記帳、法人税・消費税の申告を軸にしながら、雇用・社会保険の論点を案件ベースで吸収します。いずれの順でも、試験勉強と現場タスクを連動させると定着が加速します。
- 入口の決定:現在の職場や配属に近い資格から着手
- 現場と学習の接続:担当業務の論点を科目学習に反映
- 型の標準化:賃金台帳、勤怠、仕訳、申告のテンプレ整備
- 連携の実践:給与設計と税負担、社会保険料の整合をレビュー
- 範囲拡張:助成金、節税、組織再編など横断テーマへ展開
補足として、科目合格制を活かす場合は繁忙期を外して受験計画を引くと学習が継続しやすいです。
依頼の失敗を防ぐ!料金と見積もりチェックリストでコストダウン
依頼範囲と見積条件はここを要チェック!
依頼の初動で条件を固めるほど、ムダな追加費用は避けられます。特に社労士や税理士へ依頼する場合は、労務や税務の独占業務が絡むため、範囲の線引きが曖昧だとコストが膨らみます。まずは担当者と実務の切り分けを整理し、提供資料を確定してから見積を取得しましょう。納期は中間チェック日を含めた期日で合意し、修正回数は基本2回までなど回数と対応範囲を明記します。対応ツールは会計ソフトや勤怠システムの指定を共有し、ライセンス費用の負担者も決めておくと安全です。範囲外作業は時給または単価表で事前に設定すると追加請求を抑制できます。人事や給与計算の調整、記帳や申告作成などの線引きを表で可視化すると、交渉がスムーズになります。
| 項目 | 事前に固定化するポイント |
|---|---|
| 提供資料 | フォーマット、締切、欠損時の再提出ルール |
| 納期 | 中間レビュー日、最終納品日、遅延時の対応 |
| 修正回数 | 回数、対象範囲、再見積りの条件 |
| 対応ツール | 使用ソフト、権限付与、ライセンス費の負担 |
| 範囲外作業 | 単価表、発注フロー、緊急対応の可否 |
上記を発注書に落とし込むと、価格のブレと手戻りを最小化できます。見積の比較検討も容易になります。
- 要件定義を文章化し、独占業務の範囲を明確にする
- 前提条件と提供資料のリストを共有してから見積依頼を出す
- 修正回数と単価表を合意し、追加作業は事前発注に限定する
- ツールとデータ連携を先にテストし、納期リスクを把握する
- 月次とスポットで支払い条件を分離し、コストを可視化する
社労士は労働保険や社会保険の手続き、税理士は申告や税務代理の作成と計算が中心です。役割を踏まえた条件設計が費用対効果を高めます。
社労士と税理士の「賢い選び方」質問集
依頼先選びをサポートする実践的な質問集
給与計算や年末調整を誰に頼むかは、業務範囲の違いを押さえると迷いません。社労士は労務と社会保険、税理士は税務と会計が専門です。まずは依頼の切り分けを明確にし、顧問料に何が含まれるかを必ず確認しましょう。スポット相談は単発で解決でき便利ですが、継続的な人事・税務の調整が必要な会社は顧問契約が安心です。以下のポイントで検討すると失敗しにくく、社労士税理士の連携力も見極められます。
-
給与計算は社労士、税務反映と年末調整は税理士が得意です
-
源泉徴収票の作成は税理士が主導、社会保険の反映は社労士が調整します
-
スポット相談の相場と顧問料の範囲を事前に書面で確認しましょう
補足として、会社の規模や従業員数により、顧問の稼働時間は大きく変わります。費用は「対応範囲×頻度」で比較すると納得感が高まります。
| 項目 | 社労士に向くケース | 税理士に向くケース |
|---|---|---|
| 給与計算 | 労働保険・社会保険の適用や法改正対応が多い | 会計連動や賞与引当と整合を取りたい |
| 年末調整 | 扶養・保険料控除の従業員対応が多い | 法定調書、償却・配当等の税務一体処理 |
| 源泉徴収票 | 賃金台帳との整合チェック | 税額計算、法定調書合算・提出 |
| スポット相談 | 就業規則、助成金、人事制度の単発相談 | 申告直前の節税、記帳・申告の単発対応 |
| 顧問料の範囲 | 手続き代行、労務相談、届出作成 | 記帳代行、申告作成、税務相談 |
上記は判断材料であり、両方の顧問でワンストップ体制を組むと実務が滑らかになります。
資格取得・将来性の疑問もまるっと解決!知っておきたいQ&A
学習計画やキャリア設計で迷う方へ、難易度や免除制度を整理しました。一般に、社労士は年1回の試験で広範囲を一発で仕上げるタイプ、税理士は科目合格制で長期戦です。どちらが難しいかは適性次第ですが、税務会計の積み上げに強い人は税理士、法令横断の記憶と運用に強い人は社労士が向きます。将来性は人事・税務いずれも安定需要があり、ダブルライセンスは企業支援の幅が広がるのが強みです。
-
よくある質問と回答
- 社労士と税理士はどちらが難しいですか
社労士は一発合格のプレッシャーがあり、税理士は科目合格の長期戦です。学習時間は社労士がおおむね1,000時間前後、税理士は2,000時間超を見込みやすいです。 - 科目免除や講習の情報はありますか
社労士は所定講習や実務要件で一部免除の制度があります。税理士は大学院修了などで税法科目の免除が認められることがあります。条件は事前確認が必須です。 - 会計士や行政書士との相性は
税理士会計士は親和性が高く、監査→税務→経営の導線を作れます。社労士行政書士は人事手続きや許認可で企業設立時に相性が良いです。 - どっちが稼げるのか
平均では税理士がやや高水準になりやすい傾向がありますが、顧問の質と単価、独立地域性で大きく変わります。 - ダブルライセンスは有利ですか
労務と税務の一体運用が可能になり、顧客満足や単価向上に直結しやすいです。学習負荷は重いため計画的に進めましょう。
- 社労士と税理士はどちらが難しいですか
学習は、ゴール設定→範囲把握→過去問・演習→法改正チェックの順で進めると効率的です。資格の選択は、日々扱いたい仕事像から逆算すると筋が通ります。