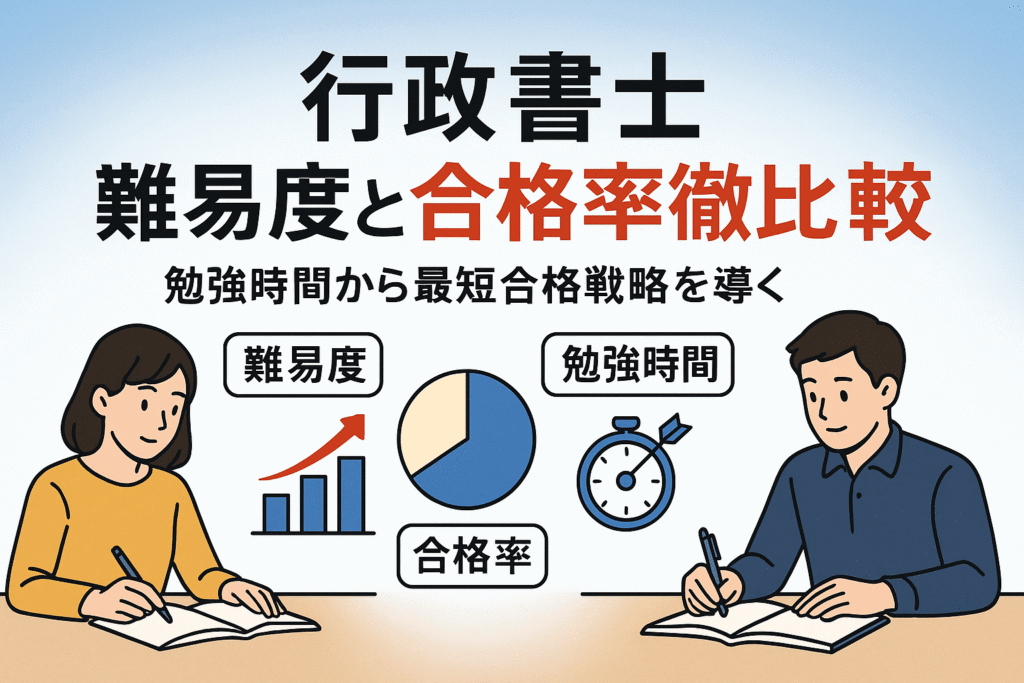行政書士は「受験資格なし」で挑戦できますが、合格率は近年おおむね10〜15%台、必要学習時間は初学者で約600〜1,000時間といわれます。科目は法令45問+一般知識14問、さらに記述式があり、総合点と科目ごとの基準点を同時に満たす必要があります。だからこそ「何から、どれだけ」進めるかが勝負です。
一方で、多くの受験生がつまずくのは民法・行政法の理解定着、一般知識の基準点未達、そして記述式の時間配分です。仕事や学業と両立しながら、どの順番で得点源を作るか、実は明確な手順があります。
本記事では、直近の合格率推移から難化・易化の波を整理し、科目別配点と出題比率を根拠に「最短で合格点に届く学習順序」を提示します。宅建士・社労士・司法書士との比較や、模試の使い方、独学と講座の選び方も具体化。法律初学者でも、半年〜1年での逆算計画が可能です。
実務と学習支援の双方に携わってきた視点で、独学者が陥りやすいボトルネックを分解し、今日から使えるチェックリストに落とし込みました。まずは、配点と基準点から導く「勝ち筋」を押さえましょう。合格率の数字に振り回されず、得点設計で主導権を取ることができます。
行政書士とは難易度をどう捉えるか 合格率と勉強時間でわかる全体像
行政書士の試験概要と合格基準を簡潔に整理
行政書士の試験は年1回実施で、法令等と一般知識等から構成されます。出題は択一と記述の二本柱です。全体の合格基準は総得点の一定比率に達し、かつ科目ごとの基準点を下回らないことが条件になります。初学者は科目横断の基礎を固めつつ、頻出領域の優先配分で学習効率を上げると良いです。近年の行政書士合格率はおおむね1割前後で推移しており、学習時間は独学で600~1000時間が目安です。難易は司法書士より低い一方で、宅建士よりは高めという評価が一般的です。独学でも合格は可能ですが、記述式の精度確保と過去問の反復が必須です。学習序盤はインプット比重を高め、直前期は問題演習で得点力を仕上げます。
-
押さえるポイント
- 法令科目での安定得点と一般知識の基準点クリア
- 記述式の答案作法と条文知識の運用
- 過去問の累積演習で出題傾向を体得
合格率の推移から見る直近の難化と易化の傾向
合格率は年度により振れ幅があり、問題の難易バランスや記述式の採点傾向で上下します。高得点者が伸びる年は易化と受け取られやすく、一般知識等で基準点未達が続くと体感難易度が上がります。受験者の平均的な受験回数は1~2回が中心で、初回で不合格だった層が弱点補強を経て次回に合格するケースが目立ちます。行政書士合格率推移を追うと、短期での劇的変化は少なく、安定した範囲内で推移しているため、学習計画の精度が結果を左右します。行政書士試験合格率大学別の話題は見られますが、最終的には学習量と質が支配的です。行政書士合格点を意識した科目別の目標設定、特に行政法と民法の取りこぼし防止が鍵になります。
| 観点 | 傾向 | 対応策 |
|---|---|---|
| 合格率の年次差 | 1割前後で安定、年により上下 | 長期計画で基礎を固定化 |
| 記述式の影響 | 採点傾向で体感難易が変動 | 事例演習で要件事実を整理 |
| 一般知識の基準点 | 未達で不合格が発生 | 時事と文章理解の対策を継続 |
テーブルの対応策を週次計画に落とし込むことで、振れ幅の影響を受けにくくなります。
行政書士の難しい点はどこか 初心者がつまずく理由
行政書士の難易の核心は、法令科目の横断理解、一般知識の科目基準、そして記述式の論点把握にあります。法令は行政法と民法の比重が高く、条文知識を単体で覚えるだけでは得点が伸びにくいです。一般知識は出題範囲が広く、得点計画が甘いと基準点割れにつながります。記述式は論点抽出と要件の正確な適用が必要で、答案の構成力が合否を分けます。独学のボトルネックは学習順序の最適化とアウトプット不足です。行政書士独学テキストと過去問、模試を連動させ、ミスの原因を記録して改善サイクルを回すと安定します。行政書士とは難易度を測るうえでは、勉強時間の質を上げる工夫が重要です。
- 法令科目の優先配分を確立する
- 一般知識の基準点対策を週次で継続する
- 記述式の型を過去問から抽出して定着させる
- 演習→復習→再演習のループで弱点を潰す
行政書士は難しいのか 科目別の難易度と配点から導く戦い方
行政法と民法を学習のメインにする理由
行政書士の得点源は行政法と民法です。近年の出題比率と配点から見ても、行政法は択一と記述で大きく占め、民法も安定して配点が高いので、最短合格を狙うならここを最優先に据えるべきです。行政法は条文の体系理解に加え、審査請求や取消訴訟などで問われる判例の判断枠組みを押さえると取りこぼしが減ります。民法は債権総論・各論、物権、親族相続のコア論点を条文横断で束ね、要件と効果を図式化して記憶の定着を図るのが有効です。過去問は肢ごとの論点を特定し、条文に戻して根拠を確認する反復が近道です。独学でもテキストと過去問、短文まとめを併用すれば得点効率が上がります。行政書士とは難易度を語る時、合格率だけでなくこの配点構造を踏まえた戦略がスコア最大化の鍵になります。
-
行政法は配点が最大級でコスパが高い
-
民法は出題の再現性が高く過去問学習が効く
-
条文横断+判例枠組みで思考時間を短縮
-
独学でも積み上げやすい範囲から優先
記述式の事案とテーマを意識した答案作成
記述式は事案を読んで要件を抽出し、事実を当てはめて結論を出す手順が重要です。まず設問のテーマを一言で定義し、関係条文と判例のキーワードを短文で決めます。次に要件を箇条化し、設問文の事実に番号を振って対応付けると失点回避がしやすくなります。書く順序は、結論、理由(要件の充足)、根拠の条文または判例の順で簡潔にまとめると安定します。過去問の反復は同テーマを3周以上行い、出題論点を自作テンプレに格納します。時間管理は一問20分を上限とし、骨子作成を5分、記述を15分で練習すると本番でも崩れません。添削を受けられない独学の場合は、模範解答の語尾と論理順を写経し、露骨な主観表現を排して法的根拠に寄せることで得点のブレを抑えられます。
- テーマの特定と根拠条文の指差し確認
- 要件の列挙と事実の番号対応
- 結論→理由→根拠の順で簡潔に記述
- 同テーマを3周以上反復しテンプレ化
- 20分配分で骨子5分・記述15分を徹底
一般知識と商法会社法の取りこぼしを減らすコツ
一般知識は基準点を下回ると不合格になるため、安定して基準点クリアを狙う設計が必要です。文章理解は短期で伸ばせる高効率領域なので、毎日2~3問の読解ドリルで得点を固定化します。時事や情報法は範囲が広い反面、頻出テーマが明確なため、直近の改正点と基本語を頻度順に押さえると効果的です。商法会社法は深追いより頻出の機関設計、設立、発行、役員責任に絞り、肢別問題で重要語をトレースして正誤判断の軸を固めます。学習時間は行政法と民法の合間にブロック化し、週間スケジュールで波及学習を回すと忘れにくくなります。行政書士難易度は配点が偏るため、得点の底上げとして一般知識と商法会社法の失点減が合格率を押し上げます。
| 項目 | 目的 | 学習法の要点 |
|---|---|---|
| 文章理解 | 基準点の柱 | 毎日2~3問、設問先読みと指示語対応で速度確保 |
| 情報法・時事 | 取りこぼし削減 | 改正ポイントと頻出語のカード化で反復 |
| 商法会社法 | ミニマム合格 | 機関・設立・発行・責任に集中し肢別演習 |
補足として、得点の山を行政法と民法で作り、一般知識と商法会社法で谷を作らない設計が、独学でも合格再現性を高めます。
行政書士の難易度を他資格と比較 宅建士や社労士や司法書士との違い
宅建士と行政書士ではどちらが難しいのか
行政書士は法律系科目の比重が高く、特に行政法と民法が得点の軸になります。宅建士も民法が出題されますが、宅建業法や権利関係、法令上の制限など実務寄りの範囲が中心です。必要勉強時間の目安は、行政書士が600〜1,000時間、宅建士は300〜500時間とされ、合格率は行政書士が約10%前後、宅建士は15〜20%前後の年が多いです。民法の理解に自信があり、文章読解と条文知識を積み上げる勉強が得意なら行政書士が向きます。短期集中と過去問反復で合格を狙う学習スタイルなら宅建士が適性です。行政書士とは難易度の捉え方として、民法の深掘りと行政法の条文・判例理解を要する点がハードルになります。宅建士合格後に行政書士へ進むと、民法の基礎が活きるため学習効率が上がります。
-
行政書士は民法と行政法の配点が重く文章処理量が多い
-
宅建士は業法と過去問対応力が成果に直結しやすい
-
自己学習時間を多く確保できる人は行政書士、短期で資格取得を狙う人は宅建士が相性良好
補足として、どちらも独学は可能ですが、インプットとアウトプットの比率設計が重要です。
司法書士や社労士との難易度比較と学習相性
司法書士は不動産登記・商業登記や民訴系科目まで広く深い出題で超難関、合格率は約4%前後の年度が多く、必要勉強時間は2,000時間超が一般的です。社労士は労働・社会保険法中心で暗記量が多く、合格率は5〜7%前後、800〜1,200時間を見込みます。行政書士は理解型と条文運用が鍵で、独学でも設計次第で現実的です。乗り換えの観点では、行政書士→司法書士は民法と手続法の基礎が活きますが、記述・書式で別次元の対策が必要です。行政書士→社労士は法令学習の素地がマッチしやすく、条文読解に強い人は好相性です。行政書士とは難易度の比較では、司法書士が最上位、次いで社労士、行政書士は中堅ポジションと捉えると現実的です。
-
司法書士は出題量と記述の負荷が突出して重い
-
社労士は法令暗記量が多く、横断整理が決め手
-
行政書士は条文理解と民法思考を磨けば独学合格も狙える
学習スタイルの自己分析を先に行うと、乗り換え時の無駄が減ります。
| 資格 | 主科目の特徴 | 合格率の目安 | 勉強時間の目安 | 学習相性 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | 行政法・民法中心の理解型 | 約10%前後 | 600〜1,000時間 | 条文運用と論理思考が得意 |
| 宅建士 | 業法・法令の過去問適合型 | 15〜20%前後 | 300〜500時間 | 反復学習と短期集中が得意 |
| 社労士 | 労社法の暗記量が多い | 5〜7%前後 | 800〜1,200時間 | 暗記と横断整理が得意 |
| 司法書士 | 登記・手続法まで広範で記述重 | 約4%前後 | 2,000時間超 | 記述対策と長期学習が得意 |
表の内容は一般的な目安であり、直近の合格率や出題傾向は必ず最新情報で確認してください。
行政書士の合格率が低い理由と一発合格率の現実
初学者の合格率が伸びない三つの要因
行政書士試験の合格率が一桁から約一割で推移する背景には、初学者特有のつまずきがあります。まず大きいのは学習計画不足です。出題比重の高い行政法と民法に時間を割けず、一般知識も後回しになりがちです。次に過去問演習量の不足で、論点の頻出パターンや肢の切り方が身につかず得点が伸びません。さらに一般知識の基準点未達が致命傷となります。法律科目で積み上げても、基準点に届かないと不合格です。頻出テーマを可視化し、出題比率に応じた学習時間を配分することが重要です。行政書士とは難易度の高い法律系国家資格という位置づけですが、科目戦略と基準点対策を同時進行で進めれば、一発合格の現実味は十分あります。
-
最優先は行政法と民法の配点対策
-
過去問と模試で本試験形式に慣れる
-
一般知識の基準点を落とさない保険科目運用
補強教材はテキストと過去問題集に絞り、反復で精度を上げると効率的です。
平均受験回数と独学割合から見る対策の優先順位
独学での挑戦者は多いものの、合格者の平均受験回数は複数回に及ぶ傾向があり、一発合格は少数派です。方針は条件で変わります。時間が限られる社会人は通信講座でスケジュールとアウトプットの型を得ると失点が減ります。自律学習が得意で費用を抑えたい人は独学中心で、弱点補強に模試と単科講座を追加します。法律初学者で講義の伴走が必要なら通学が有効です。行政書士難易度の核心は配点最適化と基準点管理にあり、模試の位置付けが鍵になります。
| 条件 | 推奨スタイル | 重点ポイント |
|---|---|---|
| 社会人で時間が少ない | 通信講座併用 | 時間割の固定化と記述式演習 |
| 法律学習経験あり | 独学中心+模試 | 過去問二周後に横断整理 |
| 法律初学者で不安が強い | 通学講座 | 毎週の到達度テストで進捗管理 |
補足として、教材は一本化して重ね解きし、理解と速度を同時に高めることが重要です。
-
模試は本試験2〜3か月前から計2〜3回
-
過去問は最低2周、誤答論点は即メモ化
-
記述式は週2本、採点基準に沿って添削確認
行政書士は独学で受かるのか 学習手段別のメリットと向く人
独学の進め方と向いている人
独学で行政書士に合格するには、合格率や配点を理解しつつ、過去問題と記述式の徹底反復を軸に学習計画を組みます。行政書士難易は中堅レベルといわれ、合格にはおよそ600〜1,000時間が目安です。行政法と民法の比重が高く、配点の大きい行政法を先行して得点源化するのが効率的です。独学の鍵は、週単位で学習量を見える化し、理解と演習を往復させることです。行政書士とは難易度の観点で見ると、初学者でも体系化が進めば得点は伸びます。向いている人は、自己管理が得意で、計画を微修正し続けられるタイプです。以下の手順で迷いを減らしましょう。
-
基本テキスト1冊に集約し、条文と趣旨を素早く把握
-
過去問3〜5年分を周回し、正誤判断の根拠を言語化
-
記述式は設問形式で答案型を固定化し、毎週採点基準を確認
独学は自由度が高い一方で、理解のズレに気づきにくい弱点があります。定期的に模試で客観指標を取り入れると、合格可能性の現在地が把握できます。
通信講座や通学の効果と活用のポイント
通信講座や通学は、学習の迷いを削り、合格までの時間を短縮しやすいのが強みです。講義で論点の重要度が可視化され、行政法の条文横断や民法の判例学習が効率化します。さらに、添削や質問対応で理解のズレを早期修正でき、弱点が固定化しにくくなります。模試やレベル別演習は合格基準に直結するため、スコアの推移を指標管理する運用が有効です。行政書士独学と比較したときの費用対効果を整理すると、短期合格を狙う社会人や主婦層に適性が高いと言えます。行政書士とは難易度が中堅でも、戦略の質で結果は変わります。
| 手段 | 強み | 向く人 |
|---|---|---|
| 通信講座 | 出題傾向を凝縮、添削と質問で弱点修正が早い | 忙しく時間が限られる人 |
| 通学 | 学習ペースが安定、直前期の模試が充実 | 対面で疑問を解決したい人 |
| 併用 | 映像で復習、教室で演習の密度を上げる | 一発合格の再現性を高めたい人 |
効果を最大化するには、模試を起点に弱点科目へ学習時間を再配分し、演習のPDCAを毎週回す運用がポイントです。
- 基礎講義の受講直後に即過去問で定着率を測る
- 添削課題で記述の型を固める、フィードバックを次週のToDoに反映
- 月1回の模試で科目別の到達度を数値化し、時間配分を調整
- 直前30日は予想論点と条文根拠の往復で失点源を封じる
通信講座や通学は、学習の質を平準化しやすいのが利点です。費用はかかりますが、合格率を押し上げる選択肢として検討する価値があります。
行政書士の勉強時間の目安とスケジュール 初心者と既学者で分けて考える
初学者は半年から一年での逆算計画が有効
行政書士の学習はまず全体像の把握が肝心です。行政書士とは難易度が中堅クラスと評され、合格率はおおむね一桁後半から一割前後の推移です。初学者は600〜1000時間を目安に、生活に合わせて週次へ落とし込みます。社会人は平日短時間と休日の長時間を組み合わせ、民法と行政法に学習時間の大半を配分します。理解中心のインプットと過去問題の反復を早期に両立させ、一般知識は頻出テーマを優先し得点の底割れを防ぎます。基礎固めは3か月で区切り、以降は演習比率を高めて記述式の型を習得します。弱点は週次で可視化し、次週に克服タスクを必ず入れることで学習の目詰まりを防ぎます。忙しい時期も毎日30分の継続を死守し、学習の断絶を起こさないことが合格に直結します。
-
社会人の時間確保策
- 通勤・休憩のスキマは判例や条文の音声再生に充てる
- 早朝60分で民法、夜30分で行政法肢別を固定化
- 休日は3コマ×90分で過去問→復習→記述演習の順に回す
補足として、行政書士難易度の本質は範囲広さと精度要求の両立です。週単位で進捗を見直す習慣が勝敗を分けます。
法学既学者は短期集中で得点源の底上げ
法学既学者は基礎法学・憲法・民法・行政法の概念理解が先行しているため、短期3〜6か月の400〜700時間で合格圏が現実的です。ポイントは得点源の底上げと失点源の封じ込みです。択一は過去10年の頻出肢を主軸に論点の言い換え耐性を鍛え、記述式は民法と行政法で答案の骨組み(要件→評価→結論)を型化します。一般知識は情報・文章理解の取りこぼしを削減し、足切り回避の安全圏を確保します。短期設計では週の前半をインプットと弱点復習、後半を模試形式の通し演習に当て、失点分析を翌週の学習計画に直結させます。司法書士難易度との比較で迷う場合は、行政書士の出題特性に合った演習密度の設計が鍵です。行政書士合格すごいと言われる理由は、広範な法領域で安定的に点を積む運用力が必要だからです。
| 区分 | 期間目安 | 週あたり時間 | 主眼 | 具体策 |
|---|---|---|---|---|
| 既学速攻 | 3か月 | 20〜25h | 記述強化 | 毎週2問を採点基準で自己添削し改善点を明文化 |
| 標準短期 | 4〜6か月 | 15〜20h | 過去問最適化 | 頻出肢の誤答ノートを作り類題で再確認 |
| 仕事多忙 | 6か月 | 10〜12h | 重点配分 | 行政法と民法に7割、一般知識と商法に3割 |
この配分は学習の再現性を高めます。合格点到達は配点戦略の徹底で現実味が増します。
行政書士の模試と解答速報の難易度をどう使うか
市販模試と予備校模試の選び方
市販模試と予備校模試は役割が異なります。市販はコスパが高く反復に強い一方で、予備校は本試験に近い設計と詳細解説が魅力です。行政書士とは難易度の感覚を掴むには、まず市販で基礎の穴を洗い出し、その後に予備校で本試験レベルの圧を体感する流れが有効です。ポイントは受験タイミングです。インプット6割が終わった段階で市販模試、直前期に予備校模試を配置すると、合格基準に対する到達度が把握しやすくなります。復習は必ず同日中に着手し、翌日までに全設問の根拠確認を完了させます。特に民法と行政法の条文・判例は、誤答の原因語句を特定し、テキストの対応ページに戻して記録すると、学習効率が上がります。独学でもこの手順なら合格に必要な学習時間の短縮が期待できます。
-
市販模試は反復用で知識の欠落を可視化できます
-
予備校模試は本試験の難易度再現と時間配分の訓練に最適です
-
同日復習と翌日根拠確認で記憶の残存率が高まります
補足として、時間管理は60分ごとの区切りで解くブロック法が有効です。
| 種別 | 主な利点 | 注意点 | 推奨タイミング |
|---|---|---|---|
| 市販模試 | コスト効率、反復容易、解説が簡潔 | 難易度が本試験より易しい場合がある | 基礎定着期(学習中盤) |
| 予備校模試 | 本試験の出題形式に近い、解説と総評が濃い | 受験費用と拘束時間が増える | 直前期(本番2~6週間前) |
| 単元別演習 | 弱点補強に特化 | 全体俯瞰がしづらい | 模試復習直後 |
短期間での伸びを狙うなら、模試の弱点を単元別演習で即時補修するのが効果的です。
- 模試を解く前に目標得点を設定し、配点の高い行政法と民法に時間を多めに配分します
- 本番と同じ環境で時間厳守、終了後すぐに誤答原因を一行でメモします
- 翌日までにテキストへ原因をひも付け、再現答案を作成して理解を定着させます
この手順は行政書士難易度の体感と合格率向上の両立に役立ちます。
解答速報の総評から当年の傾向を読み取るコツ
解答速報の価値は正答番号ではなく総評にあります。各校の総評には「出題テーマの偏り」「難易度評価」「記述の採点予想」が凝縮され、翌年対策の設計図になります。まず出題頻度が上がったテーマを抽出し、条文直問と判例知識の比率、一般知識のニュース性をチェックします。記述は論点がズレた場合でも部分点の可能性が示されるため、採点感覚を養えます。次に、時間配分の最適化です。総評で「行政法や民法が難化」とある年は、翌年の独学スケジュールで該当単元の演習比率を増やします。最後に、設問形式の変化や語句の問われ方を用語レベルでメモ化し、テキストの該当範囲にタグ付けしておくと、行政書士とは難易度の変動に左右されにくい学習ができます。合格率推移のコメントも必ず確認し、学習時間の再配分に反映させましょう。
行政書士の資格取得後の現実 年収と仕事の広がりを短く把握
受験動機とキャリアの接続を明確にする
行政書士の学習を始める前に、合格後の働き方と収入の実像を押さえると投資対効果が見えます。登録後の主業務は許認可申請、契約書や内容証明の作成、相続や在留関連の申請支援などで、企業法務の下請けや個人の生活領域の手続きが中心です。難易は「法律初学者でも計画的な学習で到達できる」レベルですが、行政法と民法の基礎を押さえたうえでの出題対策が欠かせません。独学でも合格は可能で、標準的な勉強時間は600〜1000時間が目安です。登録後の収入は雇われと独立で差が大きく、勤務は安定、開業は変動が大きい代わりに伸びしろがあります。受験動機が年収アップなら分野選定が重要で、建設業や入管、補助金支援などの需要領域を軸にすると売上の再現性が高まります。
-
雇われは固定給で安定、独立は粗利と自由度が強み
-
需要分野の選定が年収のブレを抑えるカギ
-
行政法と民法を軸に記述式・過去問で得点力を作る
学習目的を「合格」だけでなく「どの案件で収益化するか」まで具体化すると、教材や時間配分の選択を合理化できます。
| 働き方 | 収入イメージ | 向いている人 | 主な案件例 |
|---|---|---|---|
| 雇われ | 安定的で中位水準 | 安定重視・実務経験を積みたい人 | 許認可補助、書類作成、社内手続き |
| 独立 | 変動大だが伸びしろ有 | 営業と専門性を両立できる人 | 建設業許可、在留申請、補助金、相続 |
雇われで基礎を固めてから独立する二段階ルートは、リスクを抑えつつ単価を高めやすい選択肢です。
- 業務分野を一つ決め、関連法令と書式を短期で集中的に習得する
- 受験中から同分野の情報発信と実務見学で案件理解を深める
- 合格後は実績を作るために小口案件を回し、次に高単価案件へ広げる
行政書士とは何をする資格かを具体的に描けるほど学習の優先順位が明確になります。行政書士の難易度を過大評価せず、試験対策とキャリア設計を同時進行にすることで、合格直後から収入化の立ち上がりが早くなります。
行政書士とは難易度に関するよくある質問を短く解決
行政書士をとるには何年かかるのかの目安を提示
「いつから始めれば間に合うのか」を明確にするために、学習時間と受験サイクルで逆算します。行政書士の学習ボリュームは平均600〜1,000時間が目安です。社会人が平日1〜2時間、休日3時間を確保できる場合は約9〜15か月が現実的です。大学生や時間を多く取れる人なら6〜9か月で到達できます。試験は年1回なので、試験日の約10〜12か月前に開始すると安全です。独学でも合格は可能ですが、序盤でつまずくと遅れが致命的になりやすい試験です。そこで以下のポイントを押さえて、行政書士とは難易度のバランスを理解しながら、無理のないペースを設計しましょう。
-
合格率は毎年おおむね10%前後で推移するため、計画性が重要です。
-
民法・行政法が配点の中心なので、最初の3か月で基礎を固めると効率が上がります。
-
過去問演習は累計200〜300時間を目安にし、直前3か月で仕上げます。
-
独学と講座の併用はつまずきの解消が早く、時間短縮に有効です。
下記の期間別の到達イメージを参考にしてください。
| 学習期間の目安 | 週あたり学習時間 | 到達イメージ |
|---|---|---|
| 6〜9か月 | 15〜20時間 | 短期集中。基礎済みの人向け、演習量を厚めに確保 |
| 9〜12か月 | 10〜15時間 | 初学者の標準。基礎→過去問→模試の王道パターン |
| 12〜15か月 | 7〜10時間 | 忙しい社会人向け。通勤学習や音声学習で積み増し |
学習開始から試験日までの流れは次の通りです。
- 範囲把握と教材選定(2週間)で全体像を掴む。
- 基礎インプット(3〜4か月)で民法・行政法を優先して固める。
- 過去問・模試中心の演習期(3〜6か月)で得点力を高める。
- 直前調整(1か月)で弱点潰しと本番シミュレーションを行う。
行政書士難易度は「広さ×精度」のバランス勝負です。学習時間の見積もりを保守的に置き、毎週の到達確認で微調整すると、合格までの距離が短くなります。