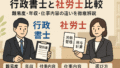日本国内で【約37万人】のみが取得している国家資格、それが一級建築士です。人口比で見ると、およそ「全国民の約330人に1人」しか持っていない、まさに建築業界のエキスパートといえる希少な資格です。
しかし、その内訳を深掘りすると見えてくるのは、「50代・60代が全体の49%超」「20代・30代はわずか13%台」という年齢層の偏りと、男性約91%・女性9%というジェンダーギャップ。大都市や大手ゼネコンに登録者が集中する一方、地方や住宅メーカーでは人材が慢性的に不足しています。
「建築士ってどのくらいの人数がいるの?」「自分はどんな働き方やキャリアを描けるの?」と感じていませんか?
これから先、資格者人口の高齢化や新規合格者の減少が続けば、建築現場の第一線を担う人材が圧倒的に足りなくなる可能性も指摘されています。
本記事では、国土交通省の公式統計や最新の登録者データに基づき、一級建築士の人数・年齢・男女比・地域・試験合格率などを徹底解説。「今、建築士をめざす意味」や将来のキャリア設計まで、気になる悩みや疑問をまるごと解消できるヒントをお届けします。
業界動向や将来展望まで読み進めることで、あなたの選択肢が確実に広がります。ぜひ、最後までご覧ください。
一級建築士は人数とは?最新統計データで徹底解説
一級建築士は全国登録者数と推移の解説
一級建築士の全国登録者数は、およそ37万人前後で推移しています。直近10年の動向を公的データから振り返ると、以下のように緩やかに増減しています。
| 年度 | 登録者数(人) | 増減幅(前年度比) |
|---|---|---|
| 2015年 | 373,000 | – |
| 2020年 | 370,000 | -3,000 |
| 2024年 | 368,000 | -2,000 |
登録人数は微減傾向にありますが、依然として建築業界内では最も権威ある資格です。新規合格者の数が一定水準を保っている一方、退職や未更新などで全体はわずかに減少傾向です。資格の希少価値は年々高まっています。
一級建築士は何人に1人?希少性と社会的意義
全国人口約1億2400万人に対し、一級建築士は約37万人。単純計算でおよそ330人に1人が一級建築士です。
-
一般的な資格と比較しても取得難易度・専門性の高さが際立つ
-
建築設計・監理だけでなく、法的な権限も持つため社会的影響が非常に大きい
-
大手建築会社に在籍している割合も高く、上場企業の技術職でも多数活躍
一級建築士は「建築士=すごい」と言われる理由のひとつが、この希少性と責任の重さにあります。業界内外での信頼が厚く、年収やキャリアにも好影響を与えています。
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の人数も比較
一級建築士の上位資格として「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」が存在します。それぞれの登録者数は以下の通りです。
| 資格 | 登録人数(2024年) |
|---|---|
| 構造設計一級建築士 | 約10,000 |
| 設備設計一級建築士 | 約8,000 |
| 一級建築士(総計) | 約368,000 |
全体に占める割合は構造設計一級建築士が約2.7%、設備設計一級建築士が約2.2%となっています。
どちらも大規模建築物設計に必須であり、専門分野での需要は右肩上がりになっています。これらの資格を持つ建築士が所属する会社は、大手企業や特殊建築物案件を多数手掛けているケースが多いのが特徴です。
年齢・性別・地域別でみる一級建築士は人数の詳細分析
一級建築士は年齢層別人数と傾向
一級建築士の登録者には50代以上が多く、業界全体の年齢構成に大きな特徴があります。2025年時点では、50代・60代が全体の半数近くを占めている状況です。新規合格者として30代が一定数いるものの、20代は全体の中でごくわずかです。
下記の年齢別登録者分布を参考にしてください。
| 年齢層 | 人数割合(目安) |
|---|---|
| 20代 | 約2% |
| 30代 | 約8% |
| 40代 | 約15% |
| 50代 | 約25% |
| 60代以上 | 約50% |
現役で働く建築士も高齢化が進んでいるため、今後の世代交代や若手人材の育成が重要な業界課題です。
男女比分析:増加する女性一級建築士は実態
建築業界では男性が多数を占めていますが、近年女性一級建築士の比率が徐々に増加しています。2024年度の統計によると、女性の割合は全体の約8%程度で、過去10年で2倍以上に伸びています。
| 性別 | 登録者割合(目安) |
|---|---|
| 男性 | 約92% |
| 女性 | 約8% |
女性一級建築士は都市部を中心に増加傾向にあり、住宅・商業施設設計やリノベーション分野で活躍の幅が拡大しています。また、今後さらに多様な現場で活躍が期待されています。
都道府県別の登録者数と地域偏差の検証
一級建築士は都市部を中心に多数登録されていますが、地方との人数差は明確です。特に東京都、大阪府、神奈川県など大都市圏に集中しており、地方都市との間には大きな開きがあります。
| 都道府県 | 登録人数(例) |
|---|---|
| 東京都 | 約42,000人 |
| 大阪府 | 約21,000人 |
| 神奈川県 | 約18,000人 |
| 北海道 | 約6,000人 |
| 沖縄県 | 約1,200人 |
都市部では大型建築物や再開発プロジェクトが多いことから、一級建築士の需要も高い傾向にあります。一方、地方では公共建築や住宅設計が中心で人数も限定的です。
若手一級建築士は人数と今後の人材育成課題
一級建築士の20代登録者の割合は全体の2%前後と非常に少なく、若年層の参入が業界の喫緊課題となっています。大学や専門学校からの新卒者が即戦力となりやすい構造ではなく、実務経験や受験資格取得がハードルとなっています。
若手人材の育成には以下のような課題が見られます。
-
長期的な実務経験が必要なため、20代での資格取得が難しい
-
難易度の高い試験が壁となっている
-
業界全体の高齢化と若手不足が続いている
今後は教育機関や企業による研修機会の拡充、業務内容のイメージアップが求められています。若手・女性建築士の増加は、建築業界の持続的な発展に直結しています。
一級建築士は資格の専門分野別人数と役割
一級建築士は日本全国で活躍する建築専門職の中でも最上位とされ、資格保持者の専門分野ごとに人数や役割が異なります。主な分野は「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」です。それぞれの人数推移と業務内容を把握することで、資格の価値や業界内で求められる理由が理解しやすくなります。
構造設計一級建築士は人数推移と業務内容詳細
構造設計一級建築士は、建築物の安全を左右する骨組み(構造)設計の専門家です。登録制度が始まって以降、登録者数は徐々に増加しており、近年の需要拡大と共に現役数も上昇傾向です。以下のテーブルは構造設計一級建築士の登録人数推移(参考年次)です。
| 年度 | 登録人数 |
|---|---|
| 2021 | 約6,200人 |
| 2022 | 約6,400人 |
| 2023 | 約6,600人 |
構造設計一級建築士の主な業務は、耐震設計・構造計算・大規模建築物の構造監理など高い専門性が求められる内容です。構造上の安全性評価や法規遵守も担当し、都市の安全を支える重要な役割を持ちます。
設備設計一級建築士は人数増加と市場ニーズ
設備設計一級建築士は、建物の快適性を担保する給排水、空調、電気設備などの計画と設計を担当します。近年の省エネや環境対策推進により、設備設計一級建築士の需要は急速に高まっています。それに伴い、資格保有者も増加しています。
| 年度 | 登録人数 |
|---|---|
| 2021 | 約5,000人 |
| 2022 | 約5,300人 |
| 2023 | 約5,500人 |
建築設備士資格とは異なり、建築確認申請時の高度な設備設計責任を持つ点が特徴です。オフィスビルや病院、学校といった大規模施設での重要な設備設計や省エネ基準への適合対応が主な職務です。
分野ごとの資格者数比較と業界における異なる役割
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の人数を比較すると、構造は約6,600人、設備は約5,500人(2023年時点)となっています。下記のテーブルで各分野の専門性と業務範囲を整理しています。
| 資格名 | 人数(2023) | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 一級建築士(全体) | 約370,000人 | 建築物の企画・設計・監理 |
| 構造設計一級建築士 | 約6,600人 | 耐震・構造設計、構造安全の監理 |
| 設備設計一級建築士 | 約5,500人 | 設備計画・省エネ設計、適合証明 |
一級建築士は総合的な設計監理を行い、その中でも構造と設備の専門資格者がより高度な分野の責任を担います。人数に大きな差はありますが、それぞれ社会的責任と貢献度が高く、業界内の役割分担が明確となっています。資格取得は、各分野で求められる深い知識と実務経験に裏打ちされたキャリアアップの証です。
大手企業・ゼネコン別の一級建築士は人数比較と特徴分析
大手ゼネコン各社の一級建築士は人数ランキング
大手ゼネコンは建築士の資格取得者数が多いことが特徴です。鹿島建設や大林組、清水建設、竹中工務店、大成建設などが業界をリードしています。下記に、主要ゼネコンの一級建築士人数ランキングをまとめました。
| 企業名 | 一級建築士の人数(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 鹿島建設 | 約2,700名 | 大規模プロジェクトを多数手掛ける |
| 大林組 | 約2,500名 | 都市開発やインフラ事業に強み |
| 清水建設 | 約2,400名 | 設計から施工まで一貫体制 |
| 竹中工務店 | 約1,900名 | デザイン性の高い建築で有名 |
| 大成建設 | 約1,800名 | グローバル事業や構造設計の実績多数 |
大手各社は数千人単位で一級建築士を有し、多様な設計・施工体制を整えています。特に鹿島建設や大林組は現場責任者や設計職だけでなく、プロジェクト管理・構造や設備設計の専門家も多数在籍している点が強みです。
住宅メーカー(住友林業・大和ハウスなど)の資格者人数傾向
住宅系大手メーカーも一級建築士資格者を多く抱えています。その中でも住友林業、大和ハウス、積水ハウスなどが上位となっています。各社の資格者数や特徴について表で整理しました。
| 企業名 | 一級建築士の人数(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 住友林業 | 約1,500名 | 木造住宅の設計力と提案力に定評 |
| 大和ハウス | 約1,300名 | 全国展開で幅広い住宅タイプに対応 |
| 積水ハウス | 約1,200名 | 独自技術と設計力、スマートハウスに強み |
| ミサワホーム | 約900名 | プレハブ住宅や独自デザインの開発が特徴 |
| パナソニックホームズ | 約800名 | 最新設備・技術を活用した住宅設計に注力 |
住宅メーカーの場合は営業・設計一体型の体制が多く、資格者が直接顧客提案や現場監理を行うことが特徴です。全国展開している企業は地域ごとのニーズに応じた設計力を重視しています。
一級建築士は多い企業の採用やキャリアパス傾向
一級建築士を多く抱える企業は採用時に資格取得者を積極的に登用し、入社後も実務経験を重ねてさらに専門分野へ進むキャリアパスを設けています。
-
新卒採用では建築学科卒業や一級建築士試験合格見込みが有利
-
既存社員には資格取得支援制度や実務経験プログラムを整備
-
設計職から構造設計・設備設計、また現場管理やプロジェクトマネージャーなど幅広いキャリア形成が可能
-
最先端プロジェクトへの参画やグローバル展開も多くのチャンスにつながる
一級建築士の資格は会社選びやキャリアアップの大きな武器となります。特に大手企業は資格による手当や昇進、専門職へのステップアップ機会も豊富です。多くの現役資格者が活躍している企業選びは、将来的な年収やキャリア形成にも大きな影響を与えます。
一級建築士は人数と業界動向:今後の課題と展望
一級建築士は人数推移の背景と影響要因分析
一級建築士は、建築の質と安全を守る重要な資格です。全国の登録人数は約37万人ですが、ここ10年ほどは微減傾向が続いています。特に、団塊世代の大量退職や、少子化による若年層減少もあり、人数推移に大きな影響を与えています。
下記のテーブルは、全国における建築士人数の推移例です。
| 年度 | 一級建築士人数 | 二級建築士人数 | 構造設計一級建築士人数 | 設備設計一級建築士人数 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 約39万人 | 約68万人 | 約7,900人 | 約3,100人 |
| 2020年 | 約38万人 | 約69万人 | 約8,500人 | 約3,500人 |
| 2025年 | 約37万人 | 約70万人 | 約9,000人 | 約3,900人 |
このように、構造や設備設計分野では徐々に専門資格者が増加していますが、全体では一級建築士資格者数の減少が見られます。
人口減少・高齢化の影響と若手不足の現状
建築業界全体が抱える課題として、人口減少と高齢化の影響が深刻です。一級建築士の年齢分布は50代以上が中心で、20代や30代の割合はわずかです。特に20代の一級建築士は全体の5%以下とされ、現役で活躍する若手が大幅に不足しています。
-
高齢層:登録者全体の約60%
-
若手(20~30代):全体の10%未満
-
現役率:一級建築士免許を持つものの、実際に企業や現場で働く人数はさらに少数
この背景には、資格取得の難易度や受験者数の減少もあり、今後も若手不足が続くと想定されています。
将来需要の予測と資格価値の変化可能性
社会インフラの老朽化対策や都市再開発、再生可能エネルギー建築需要の拡大など、一級建築士の需要は今後も高まり続ける見通しです。加えて、政府の建築士制度見直しにより、構造設計や設備設計分野での専門資格者はさらに価値を増しています。
-
都市部の再開発増加
-
耐震・省エネ設計への需要拡大
-
大手建設会社での保有者数向上
-
専門性の高い一級建築士は人材市場で高い評価
一級建築士が持つ専門知識と設計力は、これからの社会でより価値が高まります。資格保有者の年収も安定して高水準が期待され、現役で活動する建築士の選択肢やキャリアパスも広がっています。今後、一級建築士資格は建築業界内外を問わず、希少で重要な存在となるでしょう。
一級建築士はになるための試験合格率・難易度と人数動向
一級建築士は試験の受験者数と合格率推移
一級建築士試験の受験者数や合格率は、建築士資格の人気や社会的な需要の変化を反映します。最新年度では受験者数は約30,000人前後で推移し、合格者数は4,000人弱となっています。合格率はここ数年毎年10%から13%程度で安定しています。平成時代から徐々に合格率は上昇傾向にありましたが、直近では高止まりしています。下記テーブルは、近年の推移例です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,000 | 4,100 | 13.2% |
| 2023 | 30,500 | 3,950 | 12.9% |
| 2024 | 29,800 | 3,800 | 12.7% |
このように毎年1万人に満たない新規合格者しか誕生しないため、現役の一級建築士の希少性が際立ちます。
学科・設計製図試験合格率の詳細な内訳
一級建築士の合格には、学科試験と設計製図試験の双方を突破する必要があります。学科試験の合格率は近年18%前後、設計製図試験は40〜45%程度となっています。特に学科の基準点は年度で多少変動しますが、各科目ごとに合格基準点が設けられています。
| 試験区分 | 合格率(目安) | 合格基準 |
|---|---|---|
| 学科 | 18%前後 | 総合90点以上、科目ごとの最低点必要 |
| 製図 | 40~45% | 設計能力・図面精度・記述採点 |
過去5年の動きは大きな変動はなく、学科突破者がその年の製図試験へと進みます。二重の選抜が課される構造が一級建築士の難易度を高めています。
試験取得に必要な実務経験年数と受験資格条件
一級建築士の受験には、学歴や職歴に基づいた実務経験が必須です。大学の建築系卒業者の場合は2年以上、短大・高専卒業なら3年以上、専門学校は3〜4年、それ以外は7年以上の実務経験が必要となります。さらに、登録申請には合格後も書類審査と各都道府県事務所への申請手続きがあります。
-
建築士事務所に所属して実務を積み、企業依存型の傾向も強い
-
登録状況は毎年国土交通省が公表。現在全国で約37万人程度が一級建築士として登録
-
年齢構成は多くが40~60代で、20代の割合は数%と少数
就職後に取得を目指す社会人も多く、資格取得まで数年かかることが一般的です。
大学別合格実績と試験対策のポイント概要
一級建築士合格者は国公立大学・有名私立大学の卒業生が多い傾向にあります。特に東京大学、早稲田大学、京都大学などでは、毎年多数の合格者を出しています。
合格を目指す上で重要な対策は以下の通りです。
-
学科試験は過去問演習を徹底し、基礎知識の反復学習が必須
-
設計製図は資格学校・通信講座などの演習型学習が効果的
-
勤務先のサポートや試験対策講座の活用が合格率向上のカギ
全国有力大学では合格率向上のため、実践的授業やインターン連携を活用する例も増えています。学習戦略を確立することが、資格取得への近道となります。
一級建築士は資格に関するよくある質問(Q&A)を豊富に収録
一級建築士は人数に関する頻出質問とその解答例
全国の一級建築士の登録人数は30万~40万人台で推移しています。現役として設計業務に携わる方は、多く見積もっても20万人台と推定されます。日本の人口から見ると、およそ300~350人に一人程度の割合が一級建築士資格を保有している計算です。では全国規模・業界全体・企業所属別ではどのような現状なのでしょうか。
以下のテーブルで主要な人数データをまとめます。
| 区分 | 人数(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 全国登録者数 | 約37万人 | 登録免許者 |
| 現役建築士数 | 約20万人 | 設計実務に従事 |
| 構造設計一級建築士 | 約6,500人 | 法改正による新資格 |
| 設備設計一級建築士 | 約3,200人 | 特定の設備設計経験要件 |
年齢分布で最も多い世代は50代後半から60代で、20代の一級建築士は全体のわずか3%程度と非常に希少です。近年は建設業界の人材の高齢化が進んでおり、新規合格者の若返りが大きな課題となっています。
大手建設会社では数百から千人規模の一級建築士が在籍しているケースもあります。設計組織やゼネコン、住宅メーカーそれぞれの在籍建築士数の開示は企業IRなどでも注目が集まっています。
資格の社会的価値や取得後の生活変化についての問い合わせ対応
一級建築士の資格を取得すると、社会的な評価と幅広い職域へのアクセスが得られます。個人のキャリアや年収にも大きな変化が見込めるため、多くの受験者が将来を見据えて挑戦しています。
主なポイントは以下のとおりです。
-
年収面: 有資格者の平均年収は約600万~800万円のレンジとされ、業界全体でも高い水準となります。管理職や独立後の年収アップも十分期待できます。
-
生活の変化: 一級建築士は国内外で通用する資格であり、公共事業や大型プロジェクトの主担当、機関や行政の審査員など多様な働き方が可能です。
-
職業的評価: 「一級建築士はすごい」と言われる理由は、国家試験の難易度と知識・実務経験のレベルの高さです。建築分野で信頼や責任ある立場を担う上で必須の資格といえます。
一方で「やめとけ」といった声には、激務や管理責任の重さが背景にあります。しかし設計現場のやりがいや社会的誇りを大切にする方にはやりがいの大きい資格です。業界全体で資格保有者の需要は今後も続く見込みとなっています。
一級建築士は人数に関わる最新データ・信頼できる情報源の紹介と活用法
建築士登録統計の公的情報の正しい読み方
一級建築士の実際の登録人数や現役資格者数を正確に把握するためには、国土交通省や各都道府県の建築士会、日本建築士会連合会などが公表する公式データの活用が重要です。登録統計では、毎年更新される数字だけでなく、年齢層や男女別に集計された詳細なデータも確認できます。
下記は主な公的情報源とポイントです。
| 情報源 | 主な公表内容 | データ更新頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 年度ごとの一級建築士登録者数、年齢・男女別データ | 年1回 | 公式統計として最も信頼性が高い |
| 建築士会連合会 | 会員登録状況、構造・設備設計一級建築士人数 | 随時 | 専門分野の人数把握に有用 |
| 都道府県建築士会 | 地域別人数、会社別資格者情報 | 年1回 | 転職・就職活動時に参考 |
これらのデータを比較・分析することで、全国規模だけでなく会社別や地域別の傾向も把握しやすくなります。
最新試験結果情報と登録者数の関係性理解
一級建築士の人数は、毎年の試験合格者数と実際の登録者数が完全に一致するわけではありません。合格後、登録申請をしない人や資格を返納するケースも一定数存在するため、登録者数は合格者数の推移に加えて自然減も反映された数字です。
具体的には、最新の一級建築士学科・設計製図試験の合格者データと、年度ごとの登録状況を照らし合わせてみましょう。
-
合格者数と登録者数の差
- 試験合格者がすべて登録するわけではない
- 高齢化による資格返納や、他業種転職による未更新も影響
-
構造設計・設備設計一級建築士は追加試験や実務要件が存在し、人数が限定的
最新の建築士試験情報については、試験発表月ごとに発表される公式ページを定期的に参照し、合格率の推移や属性分布を併せて確認することが大切です。
情報更新の重要性と定期的なデータチェック方法
国家資格である一級建築士の登録人数データや合格率は、毎年更新されており、業界動向を正確に把握するためには最新情報を追跡していく必要があります。特に若年層の動向、構造設計・設備設計一級建築士など関連資格人数の変化も注目ポイントです。
定期的なデータチェックの方法
-
国土交通省や建築士会の公式サイトを月1回チェック
-
資格者の会社別人数を知りたい場合は、大手建設会社の公式発表や業界ニュースを確認
-
二級建築士や構造設計一級建築士など隣接資格の最新統計にも目を通す
また、建築業界誌や資格専門サイトでは、建築士の年収や会社ランキング、年齢分布などの最新分析も随時更新されています。常に情報をアップデートすることで、転職やキャリア設計、資格取得の判断材料となり、自分にとってより有益な情報活用につなげられます。