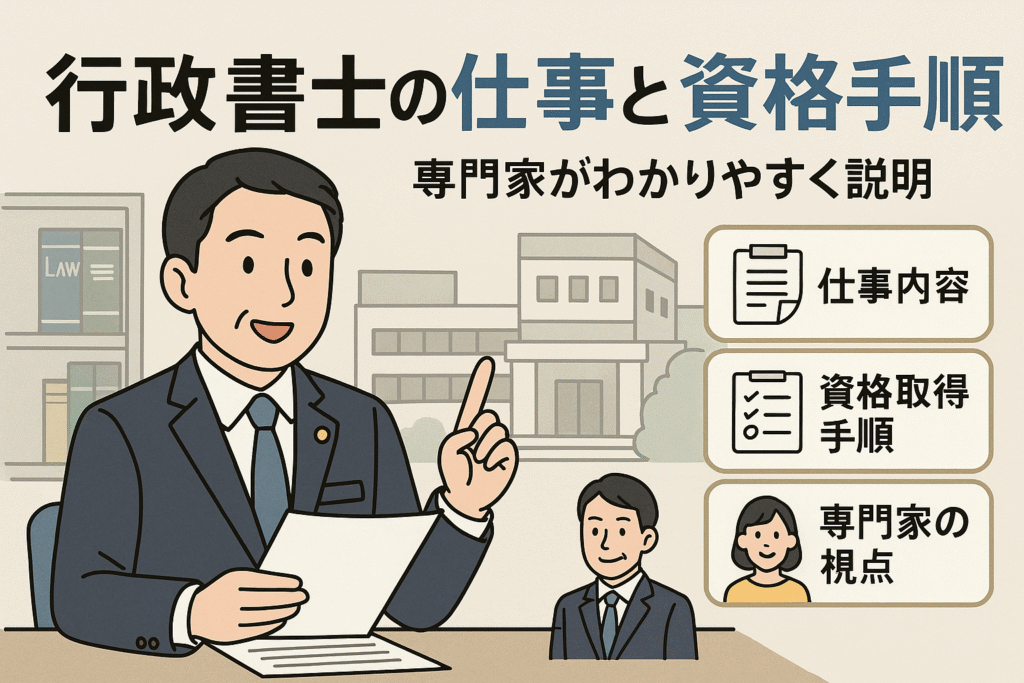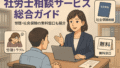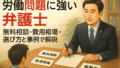「行政書士」という言葉を聞いたことはあるけれど、「実際にはどんな仕事をしているの?」と疑問に感じていませんか。実は行政書士は、全国で約5万人以上が登録する国家資格者で、毎年【4万件】を超える許認可申請サポートや各種書類の作成に関わっています。
遺言・相続・会社設立、建設業許可など、生活や事業のあらゆる場面で法律の専門家として活躍しており、「街の法律家」と呼ばれるほど身近な存在です。一方で、弁護士や司法書士、税理士との違いが分からず悩む方も少なくありません。
「独学と講座、どちらが効率的?」「行政書士の平均年収や資格の将来性は?」「どんな依頼が、どれくらいの費用で頼めるの?」といった実践的な疑問や、不安を感じているかもしれません。
この記事では行政書士とは何か、資格や業務内容、収入のリアルなデータや制度の背景まで、初めてでも分かりやすく詳しく解説します。最後までお読みいただくことで、あなたに最適な活用法や失敗しない依頼・資格取得への道筋が見えてきます。
行政書士とは何か|国家資格の基本と役割を専門的に解説
行政書士の法的定義と制度発足の歴史
行政書士は、法律に基づき官公署に提出する書類の作成や手続きの代理、相談業務を行う国家資格です。日本では1951年に行政書士法が施行され、この制度が誕生しました。法的根拠により業務範囲が明確に定められており、国民の利便性向上と手続きの効率化に大きく貢献しています。
行政書士の主な業務内容には、許認可申請、契約書や遺言書の作成、法人設立関連の書類作成などがあります。下記のテーブルで詳しく解説します。
| 主な業務例 | 説明 |
|---|---|
| 許認可申請 | 飲食店営業、建設業などの営業許可手続き代行 |
| 法人設立書類作成 | 株式会社や合同会社の設立サポート |
| 相続・遺言関連書類 | 遺産分割協議書や遺言書作成 |
街の法律家としての行政書士の社会的役割
行政書士は「街の法律家」として、日常生活やビジネスの多様な場面で市民や企業をサポートしています。身近な法律問題や手続きの相談相手として信頼されており、難解な法律文書の作成や官公署への届け出を一般市民に代わって担当します。
主な役割は以下の通りです。
-
複雑な許認可申請書類を、わかりやすい言葉で逐一解説し作成
-
家庭や個人でも対応できる相続・遺言相談
-
法改正や社会の変化に対応する最新の情報提供
行政書士の存在は、煩雑な行政手続きを円滑にし市民の負担を軽減しています。
他士業(司法書士・弁護士・税理士)との違い
行政書士と他士業の業務には明確な違いがあります。以下のテーブルで比較します。
| 資格名 | 主な担当業務 |
|---|---|
| 行政書士 | 官公署提出書類作成・各種申請手続き・相談対応 |
| 司法書士 | 不動産登記・商業登記・裁判所関係書類の作成 |
| 弁護士 | 訴訟代理・法律相談・裁判対応 |
| 税理士 | 税務申告・税務相談・会計業務 |
行政書士は主に行政手続きの専門家として、書類作成と申請代理を担います。一方、司法書士や弁護士は登記や訴訟を得意分野とし、税理士は税務や会計に特化しています。それぞれが分野ごとに強みを持ち、市民の多様なニーズに応じたサポートを提供しています。
行政書士の主な仕事内容と具体的業務一覧
行政書士は、主に法律に基づき官公署に提出する書類の作成や申請手続きの代行を行う国家資格者です。日常生活やビジネスのさまざまな場面で活躍しており、契約、遺言、許認可など幅広い業務を担っています。ここでは行政書士が担う具体的業務とその重要性についてわかりやすく紹介します。
官公署に提出する書類の作成業務の詳細
行政書士は、個人や企業からの依頼を受けて、官公署に提出するさまざまな書類を作成します。中でも許認可申請書は行政書士業務の中心であり、事業の開始や営業・サービス継続の場面で重要な役割を果たしています。
主な流れは依頼内容のヒアリングから必要事項の整理、法律や条例に沿った書類作成、提出までが含まれます。不備があると受理されないため、専門的な知識と正確性が強く求められています。
権利義務に関わる書類の種類例
権利義務に関わる書類は、多くの人々の生活や事業活動の安定に直結しています。具体例は下記の通りです。
-
契約書(売買・賃貸・業務委託など)
-
遺言書や相続関係説明図
-
内容証明郵便作成書類
これらの文書は権利・義務の明確化や争いごとの予防に不可欠であり、行政書士が慎重に作成することで信頼性が高まります。
事実証明に関する書類の役割と事例紹介
行政書士は、事実証明に関する書類も多く扱います。これらの書類は各種行政手続きや証明に活用され、信頼性が求められる重要な役割を担います。
| 書類の種類 | 主な用途例 |
|---|---|
| 実地調査報告書 | 許認可の条件確認や現況証明 |
| 内容証明文書 | トラブル防止・訴訟時の証拠 |
| 戸籍・住民票関連 | 相続や入管手続き等への添付 |
正確な事実記載と形式遵守が重要となります。
書類提出代理および申請手続き代行
行政書士は依頼者に代わって官公署へ書類を提出し、必要な申請手続きを一括して代行します。例えば飲食業の営業許可や建設業許可など、複雑な手続きをプロの立場でサポートするため、時間や手間の大幅な削減が可能です。申請内容確認や補正対応も含まれるため、多忙な経営者や個人にも大きなメリットがあります。
相談業務・予防法務としての行政書士の支援
行政書士は日常生活や事業活動における法律相談やトラブル防止策を提供しています。契約締結前のリスク診断、相続や遺言の内容アドバイスなど、未然に問題を防ぐ予防法務の重要性が高まっています。専門家の視点で丁寧なヒアリングを行い、安心を届ける存在として多くの人に求められています。
専門的・特定業務(独占業務含む)の紹介
行政書士が独占的に行える業務としては、「官公署提出書類の作成」と「提出代行」が含まれます。また、電子申請や在留資格認定など、法令に基づく高度な業務分野も拡大しています。これにより、社会やビジネスの複雑化に対応したプロフェッショナルなサポートが求められる資格となっています。
行政書士資格取得のプロセスと試験内容の深堀り
行政書士の受験資格と必要な学歴・条件
行政書士試験は、年齢や学歴、国籍に制限がなく、誰でも受験できる国家資格試験です。法律や行政分野に興味がある方や社会人、高卒・大学生も目指せる点が大きな特徴です。公務員や他の士業資格と違い、特別な実務経験や履歴書の提出も不要です。以下の点を押さえておきましょう。
-
受験資格は一切なし。学歴や年齢制限もなし
-
登録時に一定の欠格事由(刑罰歴など)がある場合は不可
-
合格後、行政書士として業務を開始する際は登録が必要
幅広い層がチャレンジできるため、再就職やキャリアアップを目指す人にも最適な資格です。
試験科目の概要と出題範囲
行政書士試験で問われる科目は、専門的かつ幅広い範囲を含みます。知識をただ暗記するだけでなく、実務に直結する法的な思考力も必要です。
| 科目 | 内容例 |
|---|---|
| 憲法 | 基本的人権・統治機構など |
| 民法 | 契約・相続・不法行為等の基本ルール |
| 行政法 | 行政手続法・行政不服申立制度など法の運用事例 |
| 商法 | 会社法・商取引に関する基礎知識 |
| 一般知識等 | 政治・経済・社会・情報通信・文章理解ほか |
この出題範囲により、行政書士の実務に必要な法律知識と、現代社会で必要とされる一般的な知見もバランスよく求められます。
試験の難易度、合格率と合格基準点の分析
行政書士試験の難易度は高めとされており、直近の合格率はおおむね10%前後で推移しています。毎年の受験者数は4万~5万人規模であり、合格基準は各科目での下限点と総合評価によって決まります。
-
合格基準点は全体の約60%(300点満点中180点)
-
法令科目での足切り、一般知識でも一定点以上の取得が必要
-
短期間での合格は難しく計画的な勉強が不可欠
数字からも分かるように、しっかりとした計画と反復学習が合格へのポイントです。
効率的な学習方法・独学とスクール比較
行政書士試験の合格を目指すには、「独学」と「資格スクール利用」のどちらか、または併用による学習が主流です。
独学のポイント
-
市販のテキスト・過去問題集を活用
-
スケジューリングし弱点補強を徹底
-
自分のペースで進められることが強み
スクール活用のメリット
-
専門講師の解説で理解が深まる
-
模試や質問フォローなどサポート充実
-
合格までのノウハウが体系化されている
自らの学習スタイルや生活環境に合わせて最適な方法を選ぶことが、行政書士合格への最短ルートです。特に法律初学者や効率重視の場合はスクール講座の活用も検討してみてください。
行政書士資格取得のメリットとキャリア形成の実際
行政書士の資格がもたらす具体的メリット
行政書士の資格には多くのメリットがあります。主なポイントは次の通りです。
- 独立開業が可能
自身で事務所を開き、クライアントからの依頼を受けて行政手続や書類作成、各種申請業務が行えます。これにより、責任ある仕事を社会に提供できます。
- 就職や転職の幅が広がる
行政書士の知識とスキルは法律事務所、企業法務部、建設業界、保険や不動産業など多岐にわたる分野で活かせます。履歴書に記載できる国家資格として、社会的信用の向上にもつながります。
- 信頼性の確立
法律に基づいて業務を行うため、顧客や企業からの信頼も得やすく、専門家として評価されることがメリットです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 独立開業 | 自分の事務所を持ち、自由な働き方ができる |
| 転職・就職に有利 | 幅広い業界・企業で専門性をアピールできる |
| 社会的信用の向上 | 国家資格として法律知識と信頼が認知される |
| 生涯にわたり活用できる | 年齢や経歴に左右されずキャリアアップが可能 |
ダブルライセンスや資格併用によるスキルアップ
行政書士は他の資格と組み合わせることで、より高い専門性や業務拡大が期待できます。特に司法書士や宅建士とのダブルライセンスが注目されています。
- 司法書士との組み合わせ
司法書士と行政書士の両資格を取得すると、会社設立手続や相続、遺言、登記申請など幅広い法務業務に携わることができます。これにより顧客層の拡大や収益向上も期待できます。
- 宅建士や社会保険労務士との併用
不動産分野や労務管理領域にも対応可能となり、ワンストップサービスの提供が可能になります。
| 組み合わせ例 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 司法書士+行政書士 | 登記手続や法律相談、相続案件など幅広く対応 |
| 宅建士+行政書士 | 不動産取引全般・許認可の申請代理業務 |
| 社労士+行政書士 | 労務・労働関連手続きの総合サポート |
複数資格を活かすことで独自の専門領域を築き、市場価値を高めることができます。
近年の需要動向と将来性について
行政書士の需要は法令改正や社会構造の変化とともに高まっており、多様な分野で活躍の場が広がっています。
- 近年の需要
建設業や運送業に関する許認可申請、外国人の在留手続き、遺言書・相続手続など専門的な知識を要する業務が増加しています。
- 将来性
少子高齢化や多様化する社会ニーズに対応できる業務が多いため、行政書士の役割は今後も拡大が予想されます。一方で、IT化や制度変更の流れもあり、従来型の業務だけでは差別化が難しくなるという課題もあります。
- 課題点も正直に
AIやデジタル化によって一部業務の効率化・自動化が進む一方、人間による判断や豊富な法的知識・経験が必要な分野は依然として需要が高いのが現状です。
行政書士は変化に柔軟に対応し、自身の強みを生かしてスキルアップを意識することが今後ますます重要となっています。
実務での収入実態と職場環境をデータと事例で解説
行政書士の平均年収と収入レンジ
行政書士の年収は活動形態や勤務先によって大きく異なります。日本行政書士会連合会の調査によると、平均年収は※約400万円前後と報告されていますが、下記のような幅広い収入層が存在します。
| 年収レンジ | 割合(目安) | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 20% | 開業初期や副業として活動するケースが多い |
| 200~500万円 | 50% | 事務所勤務や安定的な案件を持つ一般的な層 |
| 500~1,000万円 | 25% | 長年の経験や専門分野を持つ行政書士 |
| 1,000万円以上 | 5% | 大型案件や法人取引が多い独立開業者 |
行政書士は開業や独立により年収アップの可能性もありますが、安定性や手取りの面では差が大きいため、将来的な案件開拓が重要です。
就職先の種類と求人の動向分析
行政書士の就職先は民間企業、行政書士事務所、行政機関など多岐にわたります。主な職場環境を比較すると、以下のようになります。
-
民間企業の法務部門:企業内部でのコンプライアンス業務や契約書作成を担当
-
行政書士事務所:官公庁への許認可申請や各種書類作成の受託
-
独立開業:自分自身で顧客を開拓し、幅広い分野の実務に対応
-
行政機関:直接行政書士として雇用される事例は稀だが、法律関連業務で活躍するケースがある
近年、電子申請制度の普及やビザ・相続分野の需要増加で、求人や案件数は増加傾向です。特にIT、外国人雇用、企業法務に強い行政書士が選ばれる傾向にあります。反面、競争も激しく、営業力や専門分野の深堀りがキャリア継続に必須となっています。
労働環境の課題・現場のホンネを紹介
行政書士の労働環境にはやりがいだけでなく、課題や難しさもあります。
-
業務内容が幅広く、最新の法改正にも対応する必要がある
-
開業直後は顧客獲得が難しく、軌道に乗るまで時間がかかる場合も多い
-
案件によっては長時間労働や繁忙期の偏りが生じることも
実際の現場では、「営業活動が思った以上に大変だった」「相続や許認可など専門分野を確立して初めて安定した」といった声が多く聞かれます。一方で、長く働くことで信頼やリピート案件が増え、働き方の自由度も高まる職種です。
性別や年齢層別の就労状況と成功事例
行政書士は資格取得後の年齢や性別を問わず活躍できる点が大きな特徴です。特に近年は女性や異業種からの転職者、シニア世代の合格者も増えています。
下記のポイントが注目されています。
-
女性行政書士:相続や家族法分野での相談が多く、女性ならではの視点で顧客対応が強み
-
異業種転職者:営業、金融、介護業界出身者など多様なバックグラウンドを活かせる
-
シニア転職:定年後のセカンドキャリアとして行政書士を選ぶ例も
実例として、子育てと両立しながら短時間勤務を確立した女性行政書士や、前職の営業経験を活かして法人案件を拡大したケースがあるなど、多様な働き方・成功体験が生まれています。
依頼者が知りたい依頼シーンと料金・報酬体系の実態
行政書士に依頼する具体ケースの紹介
行政書士は会社設立手続きや各種許可申請、相続・遺言書の作成など、幅広い分野で業務を行っています。たとえば、建設業許可や飲食店営業許可の取得、在留資格の申請、契約書の作成支援、成年後見制度の申し立て手続きなども含まれます。これらは高い専門知識や複雑な法的手続きが必要とされるため、個人や企業が安心して依頼できる専門職と言えるでしょう。行政書士の活躍するシーンは多様で、個人のライフイベントや企業活動のサポートを担っています。
行政書士に依頼される主なケース(例)
-
会社設立や各種法人登記手続き
-
建設業・飲食業などの営業許可・認可申請
-
相続手続き、遺言書作成、財産分与サポート
-
在留資格・ビザの取得申請
-
内容証明郵便や契約関連書類の作成
-
成年後見申立てや親族関係調整の法的手続き
料金相場と報酬の決まり方
行政書士の料金・報酬は業務内容や地域、案件の難易度によって異なりますが、基本報酬に加えて着手金や追加費用が発生する場合があります。下記のテーブルはよくある依頼内容の目安をまとめたものです。
| 項目 | 料金相場(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 会社設立書類作成 | 50,000~100,000円 | 定款認証費用等は別途 |
| 建設業許可申請 | 100,000~200,000円 | 地域差や条件により変動 |
| 遺言書作成・相続相談 | 30,000~100,000円 | 公正証書作成は別料金の場合あり |
| ビザ・在留資格申請 | 50,000~150,000円 | 複雑な場合や追加書類で別途費用発生 |
-
基本報酬:業務ごとに定められた料金
-
着手金:手続開始時に必要になる事が多い
-
追加費用:必要書類が多い・複雑な案件で発生
依頼する前に見積書や契約内容の事前確認が大切です。内容や段階によって加算されることがあるため、不明点は必ず事前に相談しましょう。
依頼先の選定ポイントと注意点
行政書士を選ぶ際に重要なのは、信頼できる資格者かどうかを見極めることです。ポイントは以下のようになります。
-
行政書士登録番号や事務所情報の公開
-
分野ごとの実績や専門性の確認
-
料金やサービス内容の明確な説明
-
相談時の説明が丁寧でわかりやすいか
-
口コミや第三者評価のチェック
また、契約時は「報酬額」「業務範囲」「追加費用や納期」などを書面でしっかり確認しましょう。不明瞭な点や曖昧なものはトラブルにつながりやすいため、納得できるまで相談することが大切です。行政書士と十分なコミュニケーションを取り、自分に合った専門家を選びましょう。
よくある質問(Q&A)で行政書士への疑問を徹底解消
業務内容に関する代表的質問
行政書士は主にどんな仕事をしているのか気になる方が多いです。行政書士の仕事内容は多岐にわたりますが、特に官公署(市役所や県庁など)に提出する各種書類の作成や申請手続きの代理が中心となります。例えば、建設業の許可申請、会社設立関連の書類作成、自動車登録申請、在留資格関連手続きなど、さまざまな専門分野があります。依頼者の要望に合わせて個人や法人のサポートを幅広く提供しています。法律的な手続が苦手な方や時間がない方にとって、行政書士への依頼はスムーズかつ確実な手続きの実現に役立っています。
資格取得・試験に関する質問
行政書士になるには国家資格が必要です。試験の受験資格に年齢制限や学歴の制限はありません。試験は毎年1回実施され、法令や行政実務に関する知識が問われます。合格率は例年10%前後で、しっかりした学習が求められます。独学や通信講座、専門学校を活用して勉強する方が多く、初学者でも合格を目指しやすいのが特徴です。主な試験科目は「憲法」「行政法」「民法」などが中心ですが、文章理解や一般知識も問われるためバランス良く準備を進めることが重要です。
収入・就職事情に関する質問
行政書士の年収や就職事情は働き方によって大きく異なります。独立開業する場合、年間の収入は案件数や得意分野、営業力に左右されますが、およそ300万円から800万円程度が一般的です。勤務行政書士として企業や事務所で働く場合は安定した給与収入となるケースが多いです。行政書士資格だけで「仕事がない」と感じるケースもありますが、他の資格と組み合わせたダブルライセンスや専門分野開拓で収入アップや活躍の幅を広げている方も増えています。
行政書士の業務環境や将来性に関する質問
今後、行政書士の役割はどのように変化していくのかという点も多く質問されます。社会の複雑化や法律分野の拡大により、行政書士に求められる業務の幅は広がりつつあります。特に外国人の在留資格、相続や遺言書関連の相談、各種許可申請など、専門性が高い分野での需要が高まっています。また、IT化によるオンライン申請の拡大も業務効率化やサービス向上に寄与しており、今後も社会に求められる職種の一つとされています。
その他よくある疑問事項
-
司法書士や社会保険労務士など他士業との違いは何ですか?
-
行政書士資格で公務員にはなれますか?
-
子供でも分かるように行政書士を一言で言うと?
行政書士は「法律に強い手続きのプロ」と言われています。他の士業は登記や労務手続きを専門としますが、行政書士は日常生活やビジネスの中で書類作成と許認可申請の代理が主な活躍分野です。また資格を持っているだけでは公務員にはなれませんが、行政や法務に関する理解が深まるため、一般企業や行政機関、法律の分野で幅広い活躍のチャンスがあります。子供向けに説明するなら「困っている人の書類作りをお手伝いする人」と伝えると分かりやすいでしょう。
子供や初心者向けにやさしく解説する行政書士入門
子供向けにかみ砕いた行政書士の説明
行政書士は、いろいろな書類の作成や手続きをサポートするお仕事です。たとえば、家を建てるときやお店を始めるとき、必要な書類を書いたり、市役所などにある役所に提出するのを手伝います。法律の知識が必要なことが多く、困っている人が安心できるように助けるのが行政書士の役割です。
行政書士について小学生でもわかりやすいポイントをまとめました。
-
役所への書類を作るプロ
-
大人や会社の困りごとを助ける相談役
-
法律を身近にしてくれる先生のような存在
たとえば「ペットの店を開きたい」時、役所に出す書類を作るのを手伝ったりします。行政書士は、みんなの安心を守るお仕事です。
初心者が理解しやすい図解や例え話の提示
行政書士をもっとわかりやすくするために、身近な例え話を紹介します。
-
行政書士は「書類作成のお医者さん」
体の調子が悪いときに病院に行くように、書類や法律のことで困ったときには行政書士に相談します。
-
家を建てるときのサポート役
家を建てるときには、色々な許可や手続きが必要です。行政書士は必要な書類を書いてくれて、役所に提出までしてくれます。
行政書士が対応する書類の主な一例を下記の表にまとめました。
| 書類・手続き | 具体例 |
|---|---|
| 許認可申請 | 飲食店開業、建設業登録 |
| 各種契約書の作成 | 贈与契約、内容証明 |
| 自動車登録手続き | 車庫証明、名義変更 |
こんなふうに、行政書士はさまざまな場面で人を助けます。専門的な知識を使い、正しい手続きを安全に進めてくれます。初心者でも行政書士の仕事は「身近な困りごとを解決してくれる専門家」と理解できるでしょう。
親や指導者向けのサポート情報
子供が行政書士という職業に興味を持ったときや、将来の職業選択の参考にしたいとき、親や指導者が知っておきたい情報を紹介します。
-
行政書士になるためには国家試験に合格する必要があり、学習は独学や通信講座でも可能です。
-
法律や社会の仕組みが好きな人に向いており、幅広い年代で活躍することができます。
行政書士の主な仕事内容と必要な資質は次の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | 書類作成、申請手続き、法律相談 |
| 必要な力 | 法律知識、分かりやすく伝える力、誠実さ |
| 活躍の場 | 企業、個人、中小事業者、一般家庭 |
行政書士の仕事は世の中のルールを守り、人々の生活をサポートする大切な役割です。身近な疑問や相談ごとも気軽に話せる専門家として、頼れる存在といえるでしょう。
行政書士関連資格の比較と関連職業の理解を深める
周辺資格との業務範囲と資格難易度比較
行政書士は、官公署に提出する多様な書類の作成や申請手続きをサポートする専門家です。司法書士や宅地建物取引士(宅建士)、社会保険労務士など、同じく法的手続きに関わる資格と比較されることが多いです。各資格の業務範囲や難易度のポイントを整理しました。
| 資格名 | 主な業務 | 受験資格 | 難易度(合格率) |
|---|---|---|---|
| 行政書士 | 各種許認可、契約書作成、法人設立、遺言書作成 | 不問 | 約10〜15% |
| 司法書士 | 不動産登記、商業登記、裁判所書類作成 | 不問 | 約4〜5% |
| 宅建士 | 宅地建物取引の契約・重要説明 | 不問 | 約15〜18% |
| 社労士 | 労働・社会保険手続き代行、就業規則作成 | 学歴・実務要件 | 約6〜7% |
行政書士は「わかりやすく簡単に」説明すると、社会生活の中で発生する書類提出全般をサポートできるのが特徴です。資格取得には法律の知識が必要ですが、司法書士より難易度はやや低めです。
収入やキャリアパスの違いを具体的に示す
各士業の収入やキャリアの幅には違いがあります。行政書士は独立開業のしやすさが特徴で、顧客のニーズに応じて業務範囲を広げやすいです。一方、司法書士は登記案件など高単価業務が魅力で、高収入も期待できます。
| 資格名 | 平均年収(目安) | キャリアの広がり |
|---|---|---|
| 行政書士 | 400万円〜700万円 | 法人設立、相続、各種許認可、コンサル |
| 司法書士 | 500万円〜900万円 | 登記、成年後見、企業法務 |
| 宅建士 | 350万円〜600万円 | 不動産業企業内、営業、管理職 |
| 社労士 | 400万円〜650万円 | 労務顧問、年金相談、企業管理職 |
行政書士は、特定分野に精通し専門性を発揮することで、安定した収入を目指すことができます。社会や経済の変化にも柔軟に対応できる点が強みです。
ダブルライセンスのメリットと活用法
行政書士と他の士業資格を組み合わせる「ダブルライセンス」は、業務範囲が拡大し、多様な顧客ニーズに応えることができる大きな強みです。例えば、司法書士や宅建士と組み合わせることで、相続や不動産の一連の手続きをワンストップで提供できます。
-
メリット
- クライアントの幅広い依頼に対応
- 独自のサービス展開が可能
- 業務の繁忙期を分散できる
-
活用シーン
- 相続での登記・書類作成・遺言など一括対応
- 企業設立時に設立手続きから登記、法務相談まで総合支援
- 不動産取引における重要事項説明から契約書作成、登記まで一貫サポート
ダブルライセンスによる強みを活かせば、安定した集客や収益アップも期待でき、今後ますます重要性が高まる仕組みです。