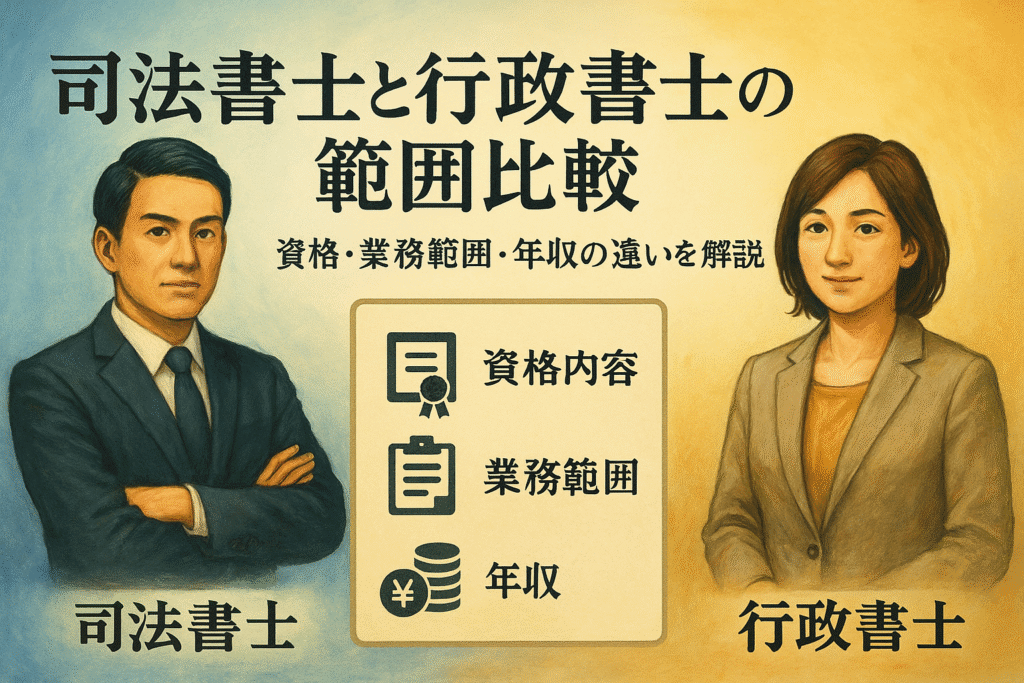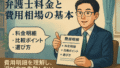「司法書士と行政書士、どちらが自分に合っているのか分からない」「実際にどんな業務を担当し、どんな資格なのか知りたい」と感じていませんか?
実は、司法書士と行政書士はどちらも法律系の国家資格ですが、その業務内容や活躍のフィールドは大きく異なります。司法書士は不動産登記や会社設立の登記申請など、年間【約180万件】もの登記業務を担っています。一方、行政書士は官公庁への許認可申請・各種書類作成を中心に、1年間で【60万件以上】の依頼を受けており、企業や個人の手続きを幅広くサポートしています。
さらに、資格試験の合格率にもはっきりとした違いがあります。司法書士試験の合格率は【4%前後】と非常に狭き門であり、法律知識だけでなく実務力も求められます。行政書士試験は近年【10%前後】の合格率となっており、難易度や学習戦略に特徴的な違いが見られます。
「自分の目指すキャリアや興味が、どちらの資格により近いのか?」を明確にしておくことは、将来への大きな一歩です。このページでは、それぞれの業務範囲や資格制度、報酬・働き方の実データまで、実体験や現場事例を交えて徹底的に比較・解説します。
仕事選びや資格取得で“損”をしないためにも、まずは両資格のリアルな違いをしっかり押さえましょう。最後までお読みいただくことで、あなたが今抱いている疑問やモヤモヤをすぐに解決できます。
司法書士と行政書士の違いを総合的に理解するための基礎知識
司法書士と行政書士の資格概要と法的立ち位置
司法書士と行政書士は、いずれも法律に基づく国家資格ですが、その目的と法的な位置付けに違いがあります。
司法書士は、法務局や裁判所の手続きに関する専門家であり、不動産や会社の登記手続き、裁判所提出書類の作成や簡易的な訴訟の代理など、主に法律上の権利や義務の明確化を支援する役割があります。
一方、行政書士は、官公署に提出する許認可申請書や契約書の作成サポート、さらに日常生活や企業活動に関わる各種書類の作成を行います。行政手続きの専門家として、市民や企業の幅広い相談に対応するのが特徴です。
どちらの資格も独占業務が存在し、特定の手続きについて資格保有者しか代理できないものがあります。
司法書士は登記関連や一部裁判手続き、行政書士は許認可申請や役所への手続きが主な活躍領域です。
【資格と法的位置付け比較】
| 資格 | 主な法的役割 | 独占業務の例 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 登記手続き・裁判所対応 | 不動産登記申請、会社設立登記、簡易裁判訴訟代理 |
| 行政書士 | 行政手続き対応、書類作成 | 官公署申請書類作成・提出代理 |
司法書士と行政書士の業務範囲の共通点と違い
司法書士と行政書士の業務範囲には一部共通点がありますが、多くのケースで取り扱う領域に明確な違いがあります。
司法書士は、不動産の所有権移転や会社設立・役員変更といった登記の専門家であり、成年後見や相続登記、簡易裁判所での代理など高い専門性と法的手続きを担います。行政書士の業務範囲はさらに広く、建設業許可や飲食店営業許可、自動車登録、内容証明など官公署への各種手続きのサポートや相談が中心です。
相続に関する業務では、司法書士が遺産分割や不動産名義変更等の登記を、行政書士が遺言書作成や相続手続き全般のコンサルティングを行うといった分担があります。
両者が連携することも多く、近年ではダブルライセンスを取得して相続、不動産、法人設立領域でワンストップサービスを目指す専門家も増えています。
【司法書士・行政書士の主な業務比較】
| 項目 | 司法書士の業務例 | 行政書士の業務例 |
|---|---|---|
| 登記 | 不動産登記、会社設立登記 | 行わない |
| 法律書類 | 裁判所提出書類、簡易裁判訴訟代理 | 官公署申請書、契約書、内容証明作成 |
| 相続・遺産 | 相続登記、成年後見開始申立 | 遺言書、相続手続きの相談・サポート |
| 手続き・許認可 | 行わない | 行政手続きの許認可(建設、飲食、在留資格など) |
| 相談・コンサル | 法律実務に関する相談 | 行政・日常業務に関する広範なコンサルティング |
両資格の違いを正しく理解し、自分の依頼や将来のキャリアに最適な専門家を選ぶための参考にしてください。
司法書士と行政書士の業務内容の詳細比較
司法書士の専門業務と具体的対応例
司法書士は主に不動産や会社の登記、裁判所提出書類作成、相続手続きなど法的手続きの専門家として活躍しています。業務の中心となる登記は、所有権移転や会社設立、役員変更、不動産の相続登記など、多くの場面で重要な役割を担います。
また、簡易裁判所における訴訟代理や、債務整理・成年後見制度への対応など、法律面から一般市民や事業者をサポートします。登記や訴訟は独占業務であり、司法書士以外は扱えません。相続分野では、遺産分割協議書の作成や遺言執行、遺産承継手続きも幅広く対応しています。
下記の比較表で司法書士の業務対応例をわかりやすくまとめます。
| 業務領域 | 対応可能な具体的内容 |
|---|---|
| 不動産登記 | 所有権移転登記、抵当権設定など |
| 商業・法人登記 | 会社設立、役員変更、解散手続き |
| 相続・遺言 | 相続登記、遺言執行、財産分割支援 |
| 簡易裁判代理 | 訴訟代理、調停、債務整理 |
| 成年後見 | 保佐・後見開始申立書類作成 |
このように、司法書士は登記や裁判関係のプロフェッショナルとして、正確かつ迅速な手続きを提供しています。
行政書士の専門業務と実務範囲
行政書士は官公庁への許認可申請書類作成・提出や、契約書、事業計画書作成などを行う行政手続きのエキスパートです。自動車登録や建設業など多種多様な許認可申請に対応でき、企業・個人を問わず幅広いニーズに応えています。
また、外国人の在留資格手続き、法人設立支援、内容証明郵便の作成や行政不服申立て対応など専門的な分野も担当します。法改正や行政手続きの複雑化により、経験豊富な行政書士の役割は年々高まっています。
業務の一部を以下にわかりやすくまとめました。
| 業務領域 | 具体的対応例 |
|---|---|
| 許認可申請 | 飲食店営業許可、建設業許可 |
| 各種契約書・書類作成 | 事業計画書、委任状、合意書 |
| 外国人手続き | 在留資格認定、国際結婚書類 |
| 法人設立・運営支援 | 定款作成、法人設立関連書類 |
| 行政手続き代理 | 行政不服申立て、内容証明の作成 |
行政書士は日常生活からビジネスまで多様なシーンでの書類作成や申請手続きで幅広く活躍しています。複雑な行政手続きを円滑に進めたい場合、行政書士の専門知識が大きな力となります。
司法書士と行政書士の資格取得に必要な試験内容・難易度・学習戦略の比較
司法書士と行政書士はそれぞれ独自の試験内容と難易度があり、対策法や適切な学習戦略も異なります。どちらの資格も法律のプロとして活躍するための専門知識が必要ですが、受験を考える際には自分に合った戦略と準備が求められます。下記のテーブルで両者の主な違いを整理しました。
| 比較項目 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 合格率 | 約3~4% | 約10% |
| 想定学習時間 | 2,000時間以上 | 600~1,000時間 |
| 試験内容 | 憲法・民法・会社法など | 憲法・民法・行政法など |
| 必要知識レベル | 高度な法律解釈・実務力 | 幅広い法律知識と事例対応 |
| 難易度 | 非常に高い | やや高い~中程度 |
試験科目や内容の違いだけでなく、出題傾向や合格までの学習方法も重要です。どちらを目指すか迷った際は、将来のキャリアや仕事内容にも注目しましょう。
司法書士試験の科目別出題範囲と学習ポイント
司法書士試験では、不動産登記法や商業登記法など独占業務に直結する分野が重視されています。特に民法や憲法、会社法といった基礎法律科目に加えて、登記実務に密着した細かな手続き理解が必要です。
-
主な試験科目
- 民法
- 不動産登記法
- 商業登記法
- 会社法
- 憲法・刑法
- 民事訴訟法、供託法
各科目で問われる内容は具体的・実務的な問題が多く、過去問題集の徹底分析と条文理解が合格のカギを握ります。特に登記は業務の中心となるため、緻密な学習計画と反復演習が重要です。
-
学習ポイント
- 民法・登記法を重点的に繰り返し学習
- 事例問題や応用問題で理解を深める
- 法改正や最新判例にも対応
出題は記述式+多肢選択式となるため、論理的な説明力も求められます。全体的に難易度が高く、短期間での合格は困難ですが、計画的な学習で十分対策できます。
行政書士試験の特徴的な科目と対策法
行政書士試験は広範な法分野をカバーし、主には行政法と民法が得点の中心です。一般知識問題や文章理解もあり、実務的な法律知識の他、現代社会への対応力も問われます。
-
主な試験科目
- 憲法
- 民法
- 行政法
- 商法・会社法
- 一般知識(時事問題・文章理解)
行政法・民法の配点が高く、基本的条文理解と過去問題の反復トレーニングが効果的です。一般知識対策としては、時事関連ニュースのチェックや文章理解力を高めておくことも有効です。
-
対策法のポイント
- 行政法・民法を優先し体系的に学習
- 一般知識は毎日少しずつ積み重ねる
- 問題集・模試を活用して得点力強化
短期間での独学チャレンジも可能ですが、効率的なカリキュラムと演習量のバランスがポイントです。初心者にも比較的取り組みやすいですが、幅広い出題範囲を満遍なく押さえる工夫が求められます。
司法書士と行政書士の年収・報酬構造・働き方の比較
平均年収と案件単価の実例データ
司法書士と行政書士では、年収や案件ごとの単価水準に明確な違いが見られます。参考になるデータや実例をもとに両者を比較すると、下表のようになります。
| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 約550万円〜800万円 | 約300万円〜600万円 |
| 案件単価 | 不動産登記:5万円前後〜/会社設立登記:10万円前後 | 許認可申請:5万円前後/内容証明作成:2万円前後 |
| 収入安定性 | 一件ごとの高単価型。繁忙期・閑散期の差が発生しやすい | 顧問契約や継続案件も多く、安定収入も狙える |
| 主なクライアント | 不動産業界・個人・会社設立時 | 企業・個人事業主・外国人サポートなど多様 |
司法書士は不動産登記や会社設立登記など高単価な案件が多く、特定分野での高収入が狙いやすい傾向があります。一方で行政書士は許認可申請や顧問契約など継続案件を積み重ねやすく、幅広い分野で平均的な案件単価となります。
年収上では平均すると司法書士が優位ですが、案件内容や営業力・地域差などで幅がある点も押さえておきましょう。
多様な働き方と収入アップの方法
両資格は独立開業はもちろん、企業勤務や副業・ダブルライセンスによる活躍など、様々な働き方が選択できます。
-
司法書士の働き方例
- 個人事務所を経営し不動産会社と連携
- 企業の法務部で社内登記やコンプライアンス業務を担当
- 社労士・行政書士などとのトリプルライセンス開業
-
行政書士の働き方例
- 許認可申請の専門家として法人と顧問契約
- 相続・遺言などライフイベント支援専門事務所
- 外国人ビザ申請や建設業許可など多ジャンルに対応
-
収入アップのポイント
- ダブルライセンス(司法書士・行政書士両資格を取得することで業務範囲が広がる)
- 不動産系や相続手続きなど、複数資格の専門知識を活かしたワンストップサービス展開
- SNSやWebを活用した集客・相談窓口の設置
- 企業と顧問契約し、定期的な収入基盤を築く
今後はサービスの多角化や専門性の強化が求められます。特に相続手続き、企業法務サポート、ダブル・トリプルライセンスを活用した総合事務所は、収入の安定や業務拡大につながりやすいのが特徴です。ニーズの変化に柔軟に対応し、自分の強みを活かす働き方を選ぶことが重要です。
司法書士と行政書士および他士業との違いと使い分け
主な士業の業務領域と依頼事例の違い
士業には司法書士、行政書士、税理士、弁護士、社会保険労務士などがあり、それぞれ業務範囲が異なります。司法書士は不動産登記や会社設立登記、相続に関する法的手続き、簡易裁判所での代理、成年後見などが専門です。行政書士は官公庁への許認可申請や各種書類作成、外国人の在留資格申請、ビジネス契約書の作成を主な業務とします。
例えば、相続で不動産の名義変更が必要な場合は司法書士に依頼し、飲食店営業の許可申請などは行政書士が担当します。他にも、税務申告や経理については税理士、労務管理は社会保険労務士、複雑な民事・刑事事件では弁護士が対応します。
| 資格 | 主な業務例 | 依頼される代表例 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産登記、商業登記、相続登記、簡裁訴訟代理 | 不動産の名義変更、相続の手続き |
| 行政書士 | 許可申請書作成、契約書作成、在留資格申請、遺言書作成 | 建設業許可申請、会社設立時の書類作成 |
| 税理士 | 税務申告、会計、法人税・所得税の申告 | 確定申告、決算業務 |
| 弁護士 | 法律相談、訴訟代理、刑事事件全般 | 離婚・相続トラブル、訴訟や交渉 |
| 社会保険労務士 | 労働保険手続き、社会保険手続き、就業規則 | 労働保険の申請、就業規則作成 |
こうした違いを把握することで、それぞれの案件に最適な専門家へ依頼でき、無駄なく手続きを進められます。特に「司法書士と行政書士の違いがわかりやすく知りたい」「どちらに相談すべきか悩んでいる」場合は、上記表を参考にすると便利です。
兼業やダブルライセンスによるメリット
司法書士と行政書士は業務範囲が一部重なり、相続・遺産承継、会社設立、不動産関連などでダブルライセンスが強みになります。ダブルライセンスを持つことで、相続手続き全般(遺言、遺産分割協議、不動産登記、許認可申請)を一括対応でき、依頼者の手間を減らすことが可能です。また、どちらの資格も独占業務により高度な専門性を求められるため、依頼者からの信頼も高くなります。
特に、以下の点がメリットとして挙げられます。
-
相続・会社設立・不動産関連案件で幅広い業務をワンストップで対応できる
-
業務分野が広がり、案件数の増加や安定した収益確保が期待できる
-
ダブルライセンスの強みを活かし、他士業との連携や顧問契約の獲得に有利
一方で、資格取得や業務拡大には学習負担と登録費用がかかりますが、それ以上にビジネスチャンスが広がる点が魅力です。年収面でも、司法書士と行政書士それぞれで300〜600万円台が一般的ですが、ダブルライセンスの活用や多資格との組み合わせによる収入アップも現実的です。トリプルライセンス(司法書士・行政書士・宅建士など)の保持者も増加しており、時代に合わせた活躍の幅が広がっています。
相続・遺言・会社設立等での司法書士と行政書士の役割分担
相続登記と遺言書作成の資格別対応範囲
相続・遺言分野では、司法書士と行政書士が担う役割は明確に異なります。司法書士は、不動産の名義変更となる相続登記を代理で申請できる唯一の資格であり、所有権移転の手続きをスムーズに進めることが可能です。行政書士にはこの「登記申請代理権」はありません。一方、遺言書の作成に関しては、両資格者とも相談・書類作成ができますが、司法書士は遺言執行者としての手続きや、家庭裁判所への成年後見申立てにも強みを持っています。行政書士は遺産分割協議書や各種相続手続きの書類作成をサポートし、主に行政に対する届出や申請の代理・代行業務を担います。
下記のように役割が整理できます。
| 業務内容 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 〇(代理可能) | × |
| 遺言書作成支援 | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書作成 | 〇 | 〇 |
| 成年後見申立代理 | 〇 | × |
| 相続手続き書類作成 | △(一部可能) | 〇 |
それぞれの強みを活かし、依頼内容によって最適な資格者を選ぶことが重要です。
会社設立手続きにおける両資格者の役割
会社設立では司法書士、行政書士それぞれ専門分野があります。司法書士は定款認証後の法人登記申請を独占的に行え、会社設立の最終段階である登記(商業登記)を代理申請できます。これにより法務局での手続きをスムーズに完結させることができます。
行政書士は、設立時の定款作成や電子定款認証に強みがあります。また、建設業や飲食業など許認可が必要な場合、行政書士が許認可申請を総合的にサポートできる点も大きな魅力です。さまざまな業種で求められる届出や申請など、設立後の継続的な行政手続きを担当できます。
| 業務内容 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 電子定款作成 | △ | 〇 |
| 定款認証手続き | △ | 〇 |
| 商業登記申請代理 | 〇(独占) | × |
| 許認可申請代理 | × | 〇 |
両資格者の連携によってワンストップで会社設立から行政手続きまで対応するケースも増えています。それぞれの専門領域を理解し、効率的に手続きを進めることがポイントです。
司法書士と行政書士のダブルライセンス・トリプルライセンスの取得と活用法
ダブルライセンスやトリプルライセンスは、法律系資格の組み合わせにより強みを発揮します。特に司法書士と行政書士を併せ持つと、不動産登記や相続、会社設立など幅広い分野で活躍が可能です。さらに宅建士や社労士を加えることで、開業時の集客力や業務対応範囲が大きく広がります。複数資格を活かすことで、依頼者の多様なニーズにワンストップで対応できる点が、現代の法律実務において大きなメリットとなっています。
ダブルライセンス取得のメリット・デメリット
司法書士・行政書士のダブルライセンスを取得することで、他資格者との差別化につながります。メリットは以下の通りです。
-
相続や会社設立など多方面で手続きの一括対応が可能
-
顧客満足度とリピート率の向上
-
登記・許認可申請・法律相談の幅広いサポートができる
-
年収アップを狙えるビジネスモデルを構築しやすい
一方、デメリットや注意点も存在します。
-
資格取得までの勉強や費用が掛かる
-
法人設立や相続案件などの競争が激化している
-
各分野での専門性維持や最新知識のアップデートが必要
テーブルで主な相違点と強みを整理します。
| 組み合わせ | 業務対応範囲 | 年収アップ | 顧客メリット |
|---|---|---|---|
| 司法書士+行政書士 | 登記+許認可+法務書類・相続対応 | 高い | ワンストップで窓口一本化 |
| 単体資格 | 単一業務のみ | 限定的 | 他士業紹介が必要 |
トリプルライセンス(宅建・社労士含む)活用事例
近年は宅建士や社労士も組み合わせた「トリプルライセンス」が注目されています。特に不動産取引や労務管理など他分野のニーズ増加に対応するため、資格の連携は強力な武器となります。
-
司法書士+行政書士+宅建士
不動産売買・賃貸借・相続登記から各種契約・許認可までフルサポート。開業や企業法務の際に相談窓口として重宝されます。
-
司法書士+行政書士+社労士
会社設立時の労務・登記手続き・行政手続きのワンストップ提供により、ビジネスの立ち上げから運営まで一括対応が実現します。
下記のようなケースで相乗効果を発揮します。
-
相続対策で不動産の名義変更と遺産分割協議書作成、許認可見直しを同時にサポート
-
企業設立時の登記申請から人事労務管理、各種申請書類まで一貫して担当
複数資格の取得は難易度こそ高いですが、多岐にわたる業務の受任や信頼性向上、安定した収入獲得に直結し、より顧客志向のサービス展開が可能になるのが最大の魅力です。
司法書士と行政書士を目指す人向けの最新情報と未来展望
直近の法改正や試験制度の変更点詳細
直近では司法書士と行政書士いずれの資格も業務範囲のさらなる明確化や、実務に直結する法改正が進行しています。例えば司法書士は、相続や成年後見制度の拡充により、不動産登記や遺産分割協議書作成、家族信託業務が増加傾向にあり、2023年には相続登記の義務化法案が成立しました。これにより、司法書士のサポートが一層求められています。
一方、行政書士に関しても、電子申請の普及や在留資格・外国人雇用の増加を背景に、専門的な行政手続きが多様化しています。2024年以降は建設業許可や自動車関連の申請など、実務で求められる知識も増え、柔軟な対応力と最新法令に基づく正確な知識が不可欠です。
試験制度もアップデートが続きます。司法書士試験では、より実務に近い出題や論点整理が重視されつつあり、行政書士試験でも法改正を反映した新傾向の問題が採用されています。
| 資格名 | 法改正・試験制度の主な変化 | 実務上の新対応事項 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記の義務化、家族信託案件増加 | 不動産・会社登記のオンライン化、成年後見対応強化 |
| 行政書士 | 電子申請拡大、在留資格手続の多様化 | 建設業許可・自動車手続きの電子化、国際業務拡大 |
AI・IT技術が士業に与える影響と今後の展望
AIやIT技術の進化は司法書士・行政書士の業務にも大きな影響を与えています。AIによる登記書類作成の自動化や、クラウドサービスを用いた契約書チェック、申請業務の効率化は現場で浸透しつつあります。これにより、書類作成や定型手続きはよりスピーディーかつ正確に処理できるようになり、人間はコンサルティングや顧客対応など、より付加価値の高い知的業務に集中できます。
IT化の進展により、行政書士向けにも電子申請やWeb面談、クラウドファイル共有などが必須ツールとなり、全国どこでも顧客とつながる新たなビジネスモデルが拡大しています。
今後は、AIが法令改正や判例を自動収集する機能や、高度なリーガルチェックを実現することで、士業全体のサービス品質が底上げされることが予想されます。逆に、専門家としての実務判断や個別事情に応じた最適な法的サポートへのニーズも高まり、AIと人間の役割分担が一層重要になります。
-
AIによる定型作業の自動化
-
オンライン相談やWeb説明会の普及
-
顧客ニーズに合わせた柔軟なサービス設計
-
専門家の判断力・交渉力の強化
資格取得後もITリテラシーや最新法改正へのキャッチアップは必須であり、司法書士・行政書士の将来性は、知識・スキル・テクノロジーを一体的に磨けるかが鍵です。
司法書士と行政書士に関するよくある質問・疑問の詳細解説
資格の難易度・合格率に関する疑問
司法書士と行政書士で最も注目されるのが、資格試験の難易度と合格率の違いです。
司法書士試験は受験者数が多いものの、合格率は例年3〜4%と非常に厳しく、学習には約2,000時間以上が必要と言われています。一方、行政書士試験は合格率が10%前後であり、学習目安は600〜1,000時間程度とされています。
出題範囲にも違いがあり、司法書士は民法・不動産登記法・会社法等、より実務寄り・専門的な内容が中心です。行政書士は法令、行政手続、一般知識と幅広くなっています。
| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 合格率 | 約3~4% | 約10% |
| 学習時間目安 | 2,000時間以上 | 600~1,000時間 |
| 出題範囲 | 民法、不動産登記法、会社法等 | 憲法、行政法、民法、一般知識等 |
難易度は司法書士が明確に上回るといえますが、どちらも独学・通信講座・専門学校など学習方法の選択肢が豊富です。
仕事の内容・働き方・年収に関する疑問
司法書士と行政書士は業務内容や収入面にも大きな違いがあります。
司法書士の主な業務は、不動産や会社の登記手続き、相続登記、遺言・成年後見業務、簡易裁判所での訴訟代理など、法律に基づく手続きや代理が中心です。
行政書士の主な業務は、行政機関への許認可申請や各種書類の作成・代理、外国人在留手続き、遺産分割協議書の作成など多岐にわたります。
| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 主な仕事 | 登記申請、相続、成年後見、会社設立、裁判所提出書類作成 | 許認可申請、各種契約書・遺産分割協議書の作成、相談業務 |
| 平均年収 | 約600~800万円(開業・地域・案件内容で差あり) | 約300~500万円(案件・地域・営業努力で差あり) |
| 働き方 | 独立開業、事務所勤務、企業内法務など | 独立開業、事務所勤務、企業内での法務職など |
司法書士は一件ごとの報酬が高い傾向で、独占業務も多いのが特徴です。行政書士は継続的な案件や顧問契約による安定も目指せますが、年収アップには営業力や専門分野の獲得が重要です。
ダブルライセンス・兼業に関するよくある質問
司法書士と行政書士のダブルライセンスを取得するメリットも数多くあります。相続や会社設立、不動産登記などで両資格を活かすことで、ワンストップで幅広い依頼に対応可能です。
ダブルライセンスを持つと一部手続きで業務の幅が広がり、他の士業(社労士・税理士・宅建士など)と連携することも容易になります。ただし、両方を十分に活かすには継続的な学習や人脈構築が不可欠です。
| 組み合わせ例 | 内容の広がり |
|---|---|
| 司法書士+行政書士 | 相続、設立、許認可など多領域の依頼に対応 |
| 司法書士+社労士 | 企業法務や人事労務分野での強み |
| 行政書士+宅建士 | 不動産取引の契約・許認可・登記までワンストップ対応 |
ダブルライセンスの年収は目標や地域にもよりますが、専門性を持ち積極的な営業を行えば1,000万円超も目指せます。比較的負担やコストも大きいため、計画的なキャリア設計が重要です。